
「人が建物に求むこと全て」を提供するアイング株式会社様。ビルメンテナンスを中心に、建物運営には欠かせないサービスを多岐にわたって展開する、業界を牽引する企業のひとつです。同社の商材は、現場で働くスタッフのサービスそのもの。そのため働く環境や従業員満足度(ES)の向上にも力を入れており、さらなる飛躍に向けて「はたLuck」を導入しました。各部門を横断した連携を可能とした、「はたLuck」の活用法に迫ります。
- 事業内容 :ビル管理、ビルメンテナンス
- 従業員数 :約1,500名(2020年2月時点)
- 利用職場数:69施設(2020年2月時点)
- 利用機能 :はたLuckアプリ
弊社の事業の要は「現場で働く人たち」。だからこそ、数千人のスタッフ一人ひとりの思いに向き合う必要がある。
定着率の向上がキモとなる業種
自社をともに成長させるパートナーとして

「はたLuck」を提案いただいた際の熱量も好印象でした。大手のすでに完成しているツールは、飲食店などでの導入実績が多く、弊社のようなビルマネジメント業に必ずしもフィットする仕様ではありません。一方で「はたLuck」は、小回りよく、私たちが実際に使った上でのフィードバックを柔軟にサービスに活かしていただけると感じました。
ツールをただ売るのではなく、「『はたLuck』を通じて一緒に御社をよりよくしていきたい」という思いが伝わったこと、そして活用のアイデアが湧いたことが、テスト導入の決め手です。
「はたLuck」導入によって、横連携の強化と新人の定着率を向上し、スタッフを大切にする企業だというスタンスを見せることができる
テスト導入で、横連携の「変化」を実感

テスト導入先に選んだのは、清掃・警備・設備・受付の4業務を請け負っている施設です。異なる業務でも、施設のお客様にとっては同じ「アイングの社員」。そのため、当たり前の業務品質を提供した上で、さらに何ができるかを考えた時、一括で請け負っているからこそ、横連携でスピーディーに対応できれば、それが他社との差別化になると考えました。実際に、ある部門が「はたLuck」に投稿すると、他部門のスタッフも情報を見れることになるため、各業務への理解が促進され、気づきが生まれたのです。例えば、清掃員でなくてもゴミを拾ったり、清掃員が釘が出ていたら設備に伝えたり、小さな気づきが横連携となって、業務品質の向上、効率化にも繋がることがわかりました。
新人が孤独を感じないためにできること

新人スタッフの”情報の孤立”を防ぐのにも一役買っています。新人は、覚えることもわからないことも多く、離職率が一番高い時期。そんな時、孤独を感じさせないことが大事なんです。「はたLuck」を見れば、マニュアルもあるし、連絡事項も流れる。最初はまず「はたLuck」を見て、慣れていけばいいという気軽さがいいんです。今後、現場品質がビジネスを左右する企業にとって、こうしたツールの導入は、現場スタッフを大切にしている企業だという姿勢を示すことができる。これって非常に重要なことだと思います。

日々の声がけで、ミドル・シニア層のスタッフにも、わずか1ヵ月で浸透。「はたLuck」をきっかけに、リアルなコミュニケーションも活性化
これまで作れなかった「繋がり」への期待

アリオ鷺宮で働く弊社スタッフは約80名。ここでは、責任者を通しての口頭での指示が、主なコミュニケーションで、毎日4部門の責任者間でミーティングを行い、そこで出た情報を伝達するスタイル。なので、部門内の繋がりはあっても、部門をまたいだ交流はほとんどありません。ただこれで十分に機能していたんですね。しかし、「はたLuck」導入の話を聞いて、これまで作れなかった部門を超えたスタッフの連携ができそうだと可能性を感じました。さらに、口下手でも良い働きをしている人は多い。そんないい人財を評価し、皆に共有できる。これは、今までにない評価のシステムにもなるという期待も感じました。
ルール設定で、日々の発信と実践を促す

スタッフの平均年齢はちょっと高め。最初のうちは「ログインしてみて」「紙の連絡ノートから変わるものだから、慣れてね」といった定期的な声掛けはもちろん、簡単なルールを設けました。「出勤したら必ず確認する」「業務情報を得たら、間違っていてもいいから発信する」「私用の連絡には使わない」といった感じで、ハードルはできる限り下げて。ただ仕事で毎回使うことで、1ヵ月ほどで浸透していきました。すると、責任者やスタッフからの業務情報の発信を見て、「それってどういう意味?」と他部門の業務内容に興味を持つ人が増え、生身のコミュニケーションも増えていきました。
現場の速報性・生産性、管理職のフォロー効率がアップ。個々の自主性と繋がりの強い組織を目指して
速報性、横連携による生産性がアップ

その後も「はたLuck」によって、速報性は格段にアップしました。例えば、自動扉が故障した際、その場にいた警備スタッフがすぐ「連絡ノート」に投稿し、それを見た受付スタッフがクライアントから言われる前に、迅速に報告できたという事例がありました。また、清掃の夜間作業の日時を見て、設備スタッフが点検時間を調整するなど、自主的に適応する機会も増え、生産性もアップしました。また、複数施設を統括する私にとって、この速報性や、見た人・見ていない人の可視化機能は、フォローアップにも効果的です。私自身、出先で「はたLuck」を見てトラブルを知ると、電話で終わるものか、行くべきかという、判断材料にもなっています。
頑張るスタッフに還元するために

普段目立たない警備スタッフが積極的に投稿したことで、認知度が上がったケースもあります。彼のおかげで、警備業務への関心や理解が深まり、横連携が強化された好例です。日々、目立たない業務でも、こうした新しい発信の形で、スタッフのレベルアップができたり、埋もれた人財を掘り起こす機会にできたことがうれしいですね。
「はたLuck」で私が目指すゴールは、横連携を強化し、スタッフレベルを向上させることで、必要最小限の責任者で維持される組織をつくること。この組織によって、原価率軽減を実現し、頑張るスタッフにもっと還元したい。それがクライアントのみならず、来店されるお客様へのサービス向上にも繋がると信じています。
はたLuckの活用ポイント💡
他部門の業務理解を深めた「専門用語クイズ」
清掃・警備・設備・受付の中でも専門用語の多い「設備」が「専門用語クイズ」をスタート。部門を越えたコミュニケーションが活発になり、業務理解も深まっている。
社内報も「はたLuck」に導入!
これまで紙に印刷して各現場に郵送していた社内報。PDF化して「はたLuck」で発信するようになり、閲覧率のアップや印刷費・郵送費のカットに繋がった。
現場まで届く福利厚生
コンサートチケット配布、自社農園の取り組みなど、福利厚生の情報を投稿することで、現場も「はたLuck」を見ているかをテスト。すると即日応募・満了するなど、現場のすみずみまで情報が届いていることが実証された。

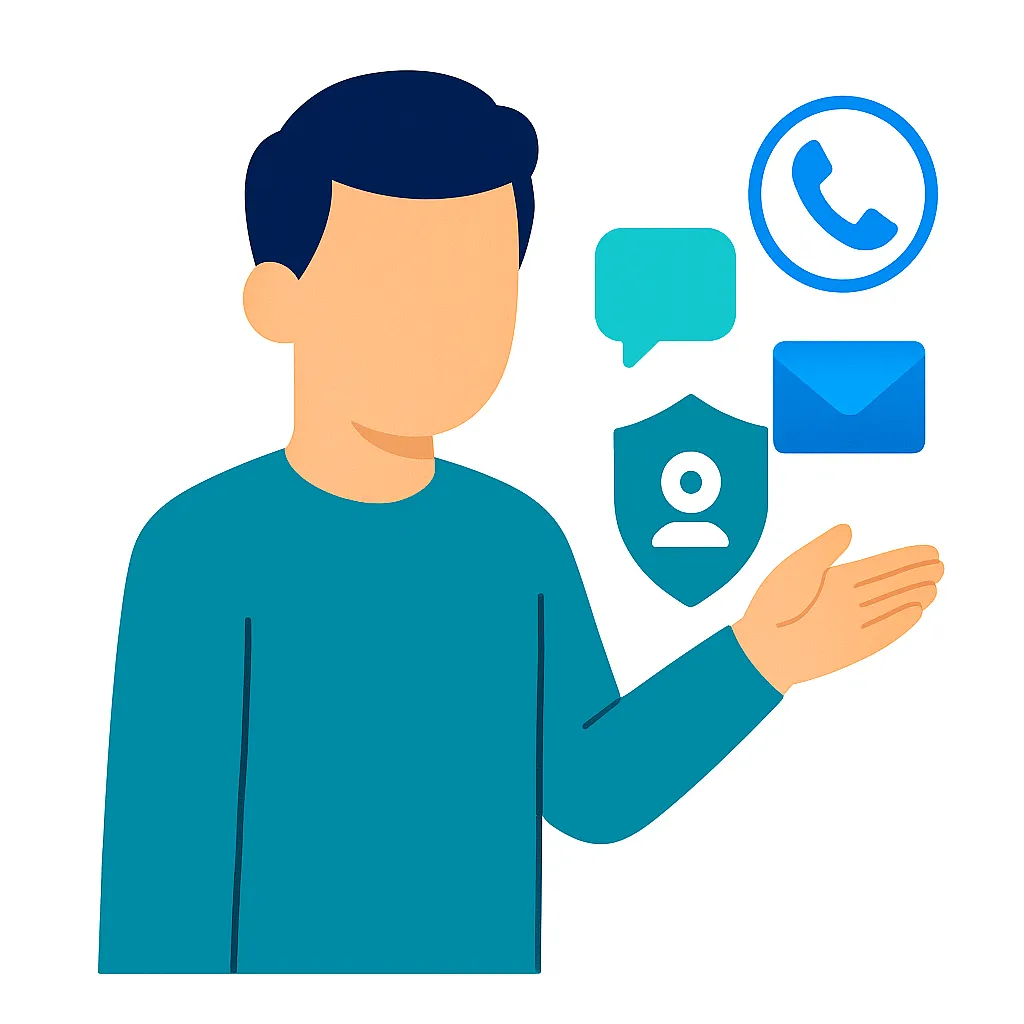







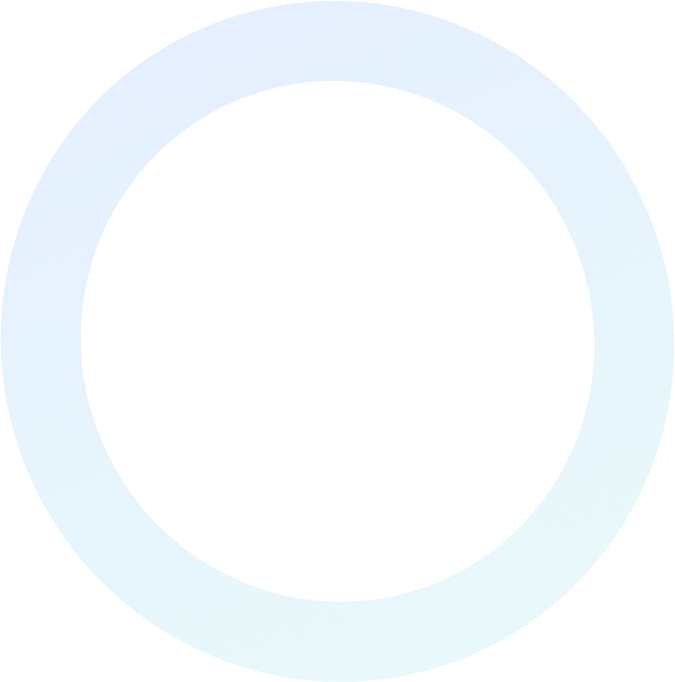







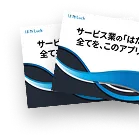
現場の仕事や品質がビジネスに直結する弊社のようなビルマネジメント業は、スタッフの定着率向上が重要です。それは長く勤める人が多いほど業務の質が上がり、採用コストも削減できるから。弊社でも、定着率の向上は積年の課題でした。できるだけ長く働いてもらいたい、そのためにも数千人いるスタッフ一人ひとりの不安や不満を吸い上げていきたい、スタッフ同士の連携を強化して業務効率化も図っていきたい…。そうした、スタッフにもっと「寄り添いたい」というのが、社長をはじめ経営陣の願いでした。こうした中で、紹介していただいたのが「はたLuck」でした。