
定食店「大戸屋ごはん処」を展開する株式会社大戸屋様。注文を受けてから一品一品丁寧にこしらえる「にっぽんの食卓ごはん」は、今や国内のみならず海外でもファンが増加しています。その味とサービスを一定のクオリティで実現し、さらに向上させていくためには、調理マニュアルをはじめ様々な情報をスムーズかつ正確に現場へ共有することが不可欠。店舗改革の一環として導入した「はたLuck」の活用事例について、本部・SV・店長の各視点からお話を伺いました。
- 事業内容 :定食店「大戸屋ごはん処」の運営
- 従業員数 :1,900名(2022年2月28日現在)
- 利用職場数:国内128店舗(2022年2月28日現在)
- 利用機能 :はたLuckアプリ
- ・情報の共有手段が統一されておらず、スタッフに情報が浸透しにくかった
- ・情報の管理・周知・浸透に多くの時間を費やしていた
- ・社員とアルバイト・パート間の情報格差が、ミスやチームワークの阻害要因となっていた
- ・マニュアルの確認が出勤時に限られており、学習機会や成長スピードが制限されていた
- ・店舗への情報共有手段を「はたLuck」に集約
- ・「連絡ノート」機能を活用し、自店舗の目標や取り組みをスタッフに向けて発信
- ・「学習する」機能を活用し、紙や動画のマニュアルをスマホで確認できる環境を構築
- ・情報発信の場を絞り込んだことで、管理側の負担が大幅に削減
- ・全員が同じ情報を見れるようになったことでミスが激減。先回りの行動など、スタッフの主体性が引き出された
- ・相互の情報発信によりチームワークが醸成。クレームが減少し顧客満足度が向上
- ・自ら学べる環境によって、スタッフの習熟スピードや品質が向上
飛び交う情報を「はたLuck」で一元化全員に情報が行き渡り、個ではなくチームで動く店舗へ
職場の多様性が当たり前になっている今、「店主の思い」をシンプルに伝えるツールが絶対必要

当時、私の担当エリアでのテスト導入となり、利便性の高い「はたLuck」を店舗スタッフが使いこなせば、絶対に良い店になると直感して、現場には「すべての機能を使い倒そう!」と声をかけました。とはいえ、店舗にただアプリを与えるだけでは浸透しません。店舗ごとにも課題も違うので、直接会って「はたLuck」の使い方を話し合い、どの店舗がどんな投稿するかを毎日ウォッチして分析して...と手探りで試行錯誤しながら定着をサポートしました。
そして、最初に成果が出たのは、とある都心の店舗でした。ここは店主が外国人で、スタッフにも外国人が多く、日本語が得意でないために接客やコミュニケーションが不十分なこともあって、毎月お客様からクレームをいただく、改善が必要な店舗でした。店主は真面目で、改善意欲もあったため、「この店の課題はこうだからこうしてみよう」と話すと、店主は本当に小まめに「はたLuck」で発信をしてくれました。すると、「改善する」という目標が皆に伝わり、毎日スタッフがローテーションで情報発信するようになりました。そうして2カ月が経った頃、なんと、クレームがピタッと止まったのです。実際に店舗を見に行くと、外国人スタッフが難しい日本語を使わずとも、お客さまを満足させる接客をしている姿を見て、本当に嬉しくなりました。他のテスト店舗でも、お客様満足度の向上が見られたり、オペレーション統一化にも大いに役立ちました。
こうした結果から見ても、店主の思いを毎日繰り返して発信することが一番大事だということを「はたLuck」から改めて教えられ、それをシンプルに実践できるツールが「はたLuck」なのだと感じます。
活用すべきは、マニュアル教育を向上させる「学習する」
コミュニケーションロスを防ぎ、フラットな情報提供を実現する「連絡ノート」

以前は、本部からくる業務や調理の紙マニュアルを大量に印刷したり、調理動画もPCしか見られないため、一人ずつ直接対面で共有するという状態。また、本部からの情報は、必要な情報だけを手で書き直して貼り出し口頭でも伝えるなど、共有・浸透には、とにかく時間と手間がかかっていました。そんな中での「はたLuck」はまさに渡りに船。まずは運用にのせるべく、出勤したら必ず「はたLuck」を見るというルールを設け、「連絡ノート」に売上・目標・連絡事項だけでなく、「○○さんが空き時間にカウンターをピカピカにしてくれました」といった良い行動・接客の観点などを、毎日投稿しました。新しい手法に抵抗を持つ年配スタッフも、その便利さに気付いてからの浸透は早かったですね。次に活用度が高い「学習する」という機能によって、マニュアル教育は格段と進化しました。
紙やPCから、スマホで見られるマニュアルへの移行は、管理側の負担を大幅に削減。出勤日の少ない学生や外国人スタッフには、好きな時に自学・復習ができる利便性が好評で、管理側も「見ました」ボタンで見た人を把握した上で教育ができるので、習熟スピードや品質はグンと向上しました。
さらに、「はたLuck」での情報共有で、スタッフの意識が上がりました。今まで、店主・社員だけが知っていて、スタッフが「聞いてない」という情報格差によってミスが発生し、雰囲気が悪くなるケースを何度も見てきました。でも、「はたLuck」はフラットに情報伝達できることで、そうした伝達ミスが劇的に減り、むしろ私より先に「明日からこのクーポン始まりますね」と情報をキャッチアップしてくれたり、スタッフ自ら、お客さまのために考え、動こうという意識が向上したと感じます。
規模、人、質ともにめざすはナンバー1。その実現に向けて「はたLuck」を仕掛けていく
今後、目指すべきものは何でしょうか?

私は、どのスタッフでも、どの時間帯でも、どの曜日でも、お客さまに「いいね」と喜んでいただける店舗を実現したい。そのためには、情報共有が大切です。情報共有に有効な「はたLuck」があってこそ、お客さまのために協力し合える関係性を作ることができました。次のステップは、「はたLuck」でスタッフの良さを引き出し、彼らの成長のために活用できればと思っています。

私は、大戸屋を日本一の会社にする、それしかないです。その実現には現場の力が必須ですから、立場として視界が上がっても、現場はしっかりと見ていたいんです。特に私が店主の時から大切にしてきたのが、コミュニケーション。「はたLuck」が、これまで見えづらかった現場のコミュニケーションを可視化してくれることで、スタッフの定着率やお客様満足度などとの相関性を探り、数値化できたら大きな前進になると思っています。

私も目指すところは1つで、まずグループとして一番になること。他の販社が大戸屋がやっていることを真似したいとか、キャリアの中で大戸屋に入りたいなど、規模も人も質も一番になりたいのです。その仕掛けの1つが「はたLuck」であり、まずは「はたLuck」での成功事例をつくり上げたい。まだまだ店舗には考える力が弱い部分もありますから、成功事例を横展開して、その幅が広がっていくのがベストです。店舗内の事例から、店舗間、地区間の相乗効果へと広がれば、間違いなく大戸屋全体の数字が変わります。今後も変化を続ける大戸屋に、ぜひ注目していただければと思います。

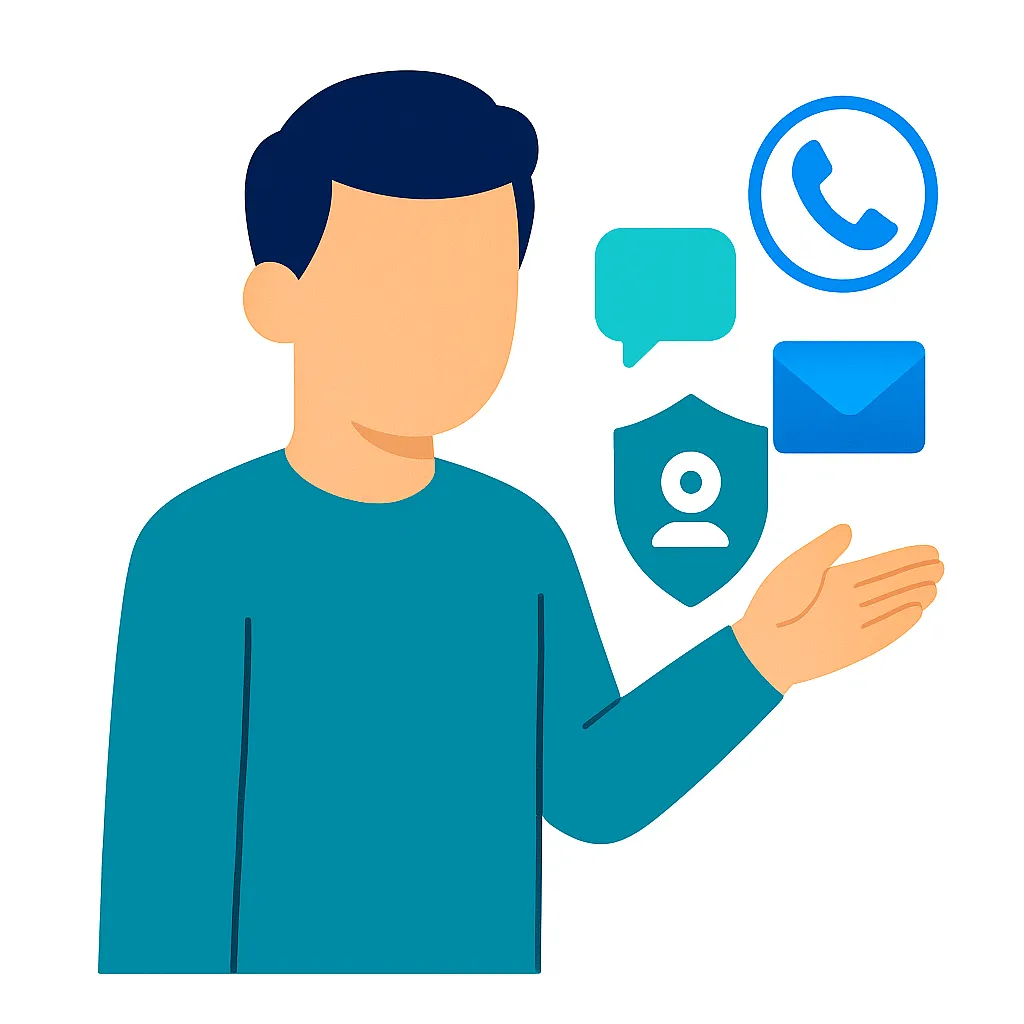






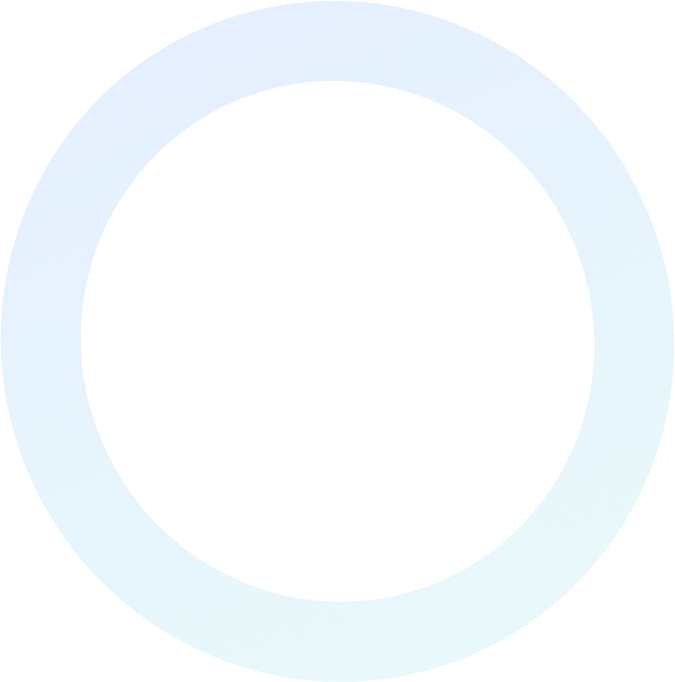





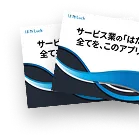
もともとは本部が店舗へ配布しているマニュアルをデジタルで一括配信・管理することができるツールを探していました。「はたLuck」は、マニュアルの展開以外にも、店舗で必要な情報伝達の機能が一つに集約されていることを知り、興味を持ったことが導入のきっかけです。
導入前は、店舗内の情報共有ツールがバラバラだったことが課題でした。チャット、教育動画の閲覧など、様々な情報がいろんな手段で展開されており、店舗スタッフは店内PCや掲示物で情報を取りに行かないといけない。情報源が2つ、3つと増えると心に残るわけがないですし、管理側も本当に大変でした。早速、10店舗にテスト導入したところ、調理動画や業務マニュアルが閲覧できる「学習する」機能、「星を贈る」という称賛や感謝をしあえる機能、「連絡ノート」を通じた情報発信が1つのアプリに集約されていたこと、さらに本部側もその内容をキャッチアップできるところが大きく評価できました。
膨大な調理マニュアルが手元で見られる、これは些細なことですが教育サイクルを回す上でキーになりますし、本部や店主が目標を発信し、スタッフも目標に向けて自由に発信して楽しんでいることがわかりました。
アンケートでも「今後も使いたい」という回答が8割を超え、店舗にとってもなくてはならないアプリになったと思っています。本部もスタッフもメリットを十分に享受できていると感じ、全店舗展開に踏み切りました。