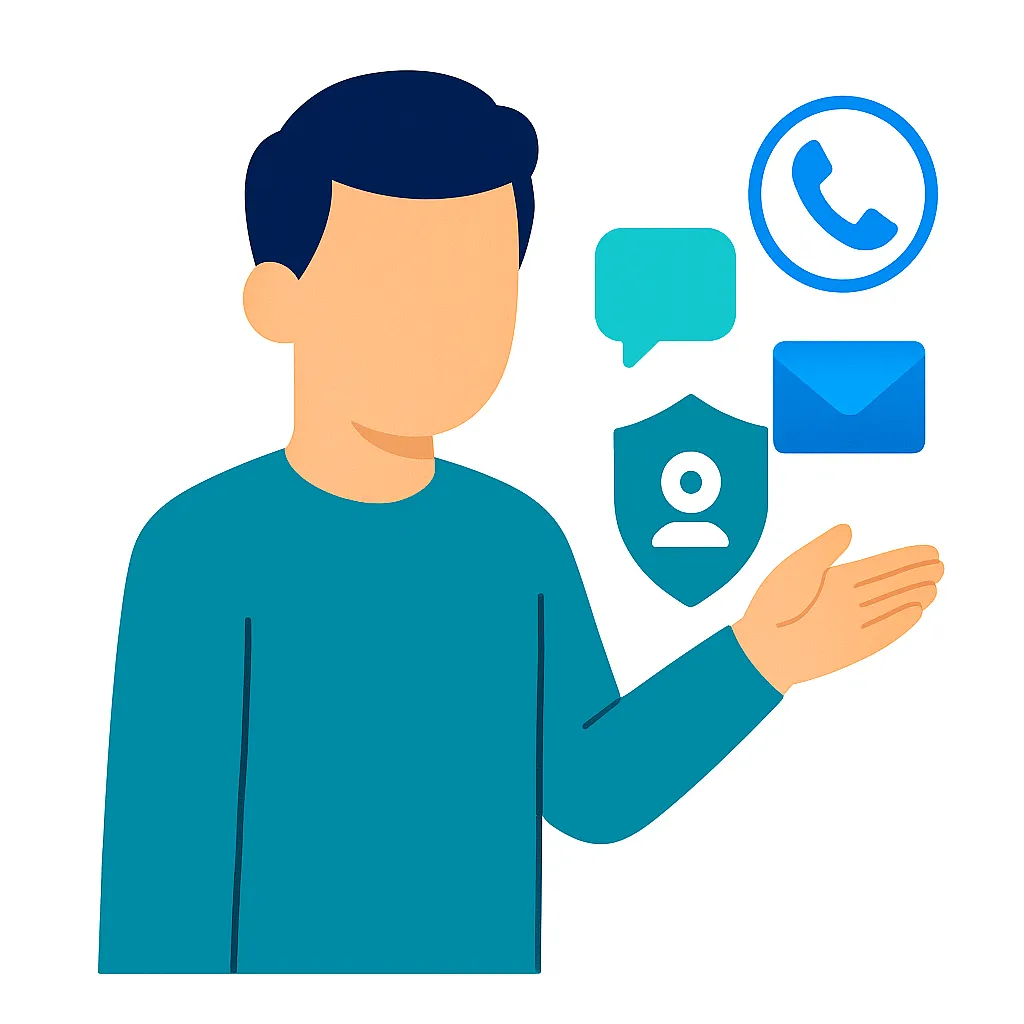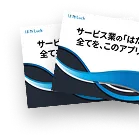業務マニュアルの作り方とは?コツや手順をわかりやすく解説
業務効率化を図る上で欠かせないマニュアル作り。しかし、具体的にどう作ったらいいのか悩んでいる人も少なくないでしょう。マニュアルを作る際は目的を明確にし、順序よく作成することが大切です。
今回の記事ではマニュアル作成のコツや手順についてわかりやすくご紹介します。
はたLuckサービス概要資料、導入事例集

店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。
目次
業務マニュアルを作る目的
より成果の出やすいマニュアルを作成するためにも、まずはマニュアルを作る目的を確認しましょう。
業務マニュアルを作成する目的は、業務をスムーズに遂行することや仕事の質を均一化すること、また効率化やコスト削減などがあります。そのために作業内容や手順を伝えるものが、マニュアルです。
職場には多くの従業員が存在し、個人によって判断基準や考え方が異なります。 仕事の進め方を統一せずに各従業員のやり方に任せていると、完成する商品や提供するサービスが異なるものになるうえ、効率も悪くなってしまいます。しかし、それでは企業として成り立たない場面も多いでしょう。
業務をマニュアルとしてまとめることで、業務品質の維持・向上を図れます。さらに、基本的な業務手順はもちろん、業務担当者の経験に基づくコツや知識についても共有することで、業務担当者でなくても一定以上の品質で商品やサービスを提供できるでしょう。
業務マニュアルの作成がもたらす効果
では、業務マニュアルを作成するとどういった効果が期待できるのか、解説します。
業務の属人化を防ぐ
業務マニュアルを整備することで、社内で属人化していた業務を減らすことができます。
「この仕事はAさんしかわからない(できない)」といった業務が多いと、その人が体調不良で休んでしまったときに業務が回らなくなってしまう可能性も否定できません。そういった場合に、業務マニュアルがあれば誰でも手順に従って業務を進められるので、このような属人化のリスクを低減できるのです。
業務効率が向上する
業務マニュアルの主な目的のひとつとして「業務の効率化」も挙げられます。業務マニュアルがあることで、業務の最中に作業手順で行き詰まったり、悩んだりする時間を削減できます。
また、業務マニュアルを参照することで、ミスの予防や確認する側のチェック工数の削減にもつながるでしょう。
効率的に人材育成ができる
業務マニュアルがあると、新入社員や異動してきた社員の教育にかける時間が減るため、教育コストを削減できます。マニュアル化することで業務が標準化され、「教える人によって手順が異なる」といったリスクも減らすことができます。
業務マニュアルの作り方

業務マニュアルを作成する際は、どのような手順で進めればよいのでしょうか。順番に見ていきましょう。
手順①利用目的や利用者を明らかにする
業務マニュアルを作成するときには、まず業務マニュアルを使う対象者と目的を明確にしましょう。マニュアルは業務の手順だけでなく、記載内容が多岐にわたることが特徴です。
そのため、対象者と目的を明確にしておかないと記載内容に一貫性がなくなる可能性があり、読み手に伝えたいことが伝わらなくなってしまいます。
使用対象者になりうるのは、たとえば管理職など従業員を教育する立場の人や、お客様と直接接したり、商品を作ったりする現場スタッフなど、さまざまです。
現場のスタッフが対象であれば、実際の作業を想定し、より細かいチェックリストなども必要になります。一方で管理職が対象であれば、現場レベルでの細かい視点だけではなく、部署全体や会社全体を俯瞰し、広い視野で物事を進められるようなマニュアルであるべきでしょう。
また、効率化やコスト削減を目的としたマニュアルなのか、業務の質を保つことが目的なのかによって、注力すべきポイントも変わります。
手順②業務マニュアル作成のスケジュールを決める
何も考えずに業務マニュアルの作成に取りかかると作成途中で挫折してしまったり、マニュアルが必要な時期に間に合わないといった事態になりかねません。そのため、着手する前にマニュアル作成のスケジュールを決めることが大切です。
完成期日から逆算するほか、通常業務以外にどの程度の時間をマニュアル作成に費やせるのか考えるようにしましょう。
また、作業開始日や完成日、かかる日数などを計画するだけではなく、業務マニュアル作成の工程を細かく区切り、いつまでにどの段階まで終わらせる必要があるかを決めておくことがポイントとなります。タスクを細かく分けて日程を決めておくことによって、現在の状況がスケジュールどおり進んでいるかどうかを確認できます。
予定よりも遅れていることが途中でわかれば、その段階で計画を再調整することが可能です。完成予定日を設定し直すか、あるいは期日を変更しないのであれば、スピードアップを図るか作業内容の見直しなどが必要になるでしょう。
業務マニュアル作成に携わる人数を増やして遅れを取り戻すことも方法のひとつです。スケジュールを決める際は、工数だけでなく人材が確保できるかどうかもあわせてチェックしておく必要があります。
手順③業務内容の棚卸しを行う
業務内容を洗い出す
目的とスケジュール感が明確になったら、業務マニュアルに記載する業務の内容を整理しましょう。業務内容の洗い出しをする際は現場の担当者にきちんと話を聞くことに加え、上司にもその内容で漏れがないかどうか確認してもらうようにしましょう。
1つの部署やポジションで行うべき業務は膨大な量であることが予想されるため、ここでの棚卸しが業務マニュアルの精度を左右するといえます。 たとえば営業担当者であれば、店頭での接客のほか、DMを活用したフォローや顧客育成、集客イベントの開催など、業務内容は多岐に渡ります。それらを一つずつ書き出していきましょう。
作業工程や手順を整理する
さらに、それぞれの業務内容の作業手順を整理します。店頭での接客なら「初回来店のお客様には何をどのような順番で説明するか」「どのような内容をヒアリングする必要があるか」などを具体的にしておきましょう。集客後のDMについては「どのツールを使い、どのタイミングで、どのような内容を送るか」といった手順もマニュアル化できます。
このような業務は、マニュアルがなければ担当者個人の感覚で行われる傾向があります。しかし、ベストなタイミングや方法、手順などを細かく決めておくことによって、誰が実行しても一定の成果を得ることが可能になるのです。 その効果を得るために業務内容の棚卸しをし、重要なポイントや効率の良い手順を明らかにしておきましょう。
作業に必要なものを洗い出す
作業手順を明確にしたら、必要なものも書き出しておきましょう。業務マニュアルには工程だけでなく、使用するものもあわせて記載するためです。
実際に作業する様子を見たり、思い出したりしながら、使っているものを書き出します。
例として、以下のような項目で、それぞれ必要なものを洗い出していきます。
- 使用するツール
- 道具や機械
- 必要な書類・資料・伝票など
- 書類の原紙・サンプル
- データ・ファイル
- 担当者名・連絡先
作業ごとの懸念点・注意点を洗い出す
マニュアルには手順や必要なものだけでなく、注意点も記載するようにしましょう。あらかじめ記載しておくことによって、同じ失敗を未然に防ぐことができるからです。
結果的に仕事の質が上がって、顧客満足度や売上アップにもつながりやすくなります。また教育面を考えても、注意すべき点は先に伝えておいた方が良いでしょう。
そのために作業工程ごとの懸念点も洗い出しておきます。
手順④構成案(目次・見出しなどの骨組み)を決定する
業務内容の棚卸しが完了したら、本文を書き始める前に構成案を作りましょう。構成案とは、マニュアルの骨組みのようなものです。本の目次をイメージすると 分かりやすいかもしれません。
構成案を作らずに本文を書き始めると、方向性が定まらずにわかりにくい内容になってしまったり、書くべき項目が漏れていたりすることがあります。そうなるのを避けるため、はじめに構成案を作ります。
構成作りの大まかな流れは、以下の通りです。
- 記載すべき項目を ピックアップする
- ピックアップした項目を大分類にグルーピングする
- 大分類の中でさらに細かく分類して目次を作る
前の手順③で洗い出した項目の中から、業務マニュアルに記載すべき内容をピックアップします。
次に、ピックアップした内容をいきなりひとつずつ順番に並べるのではなく、まずは大きな分類に分けます。似たような項目をグルーピングするイメージです。
たとえば飲食店の業務マニュアル なら、洗い出した項目をホールスタッフ用や厨房用などに分類するといったイメージです。
さらにその大分類の中で細かい作業ごとに分類します。分類したものを分かりやすい順番に並べて、目次を作っていきましょう。
手順⑤本文を作成する
構成や見出しが完成したら、本文を作成していきましょう。本文作成時のポイントは以下のとおりです。
- トラブルやイレギュラーへの対応を盛り込む
- 必要に応じて画像や動画を入れる
- 専門用語には注釈をつける
業務マニュアルには、想定されるトラブルの対応例も補足で盛り込むようにしましょう。過去のミスやトラブルがなぜ起きてしまったのか、どのように対応したのかを記載することで、同様の事態が起こることを防げます。
また、新入社員にも理解できるように難しい言葉には解説をつけ、画像や動画を用いて視覚的に分かりやすくすることも大切です。
本文作成の際には、フォーマットやレイアウトなどの大まかなデザインをあらかじめ決めておくとスムーズに進む上に、作成後に調整する際に軽微な変更で済みます。WordやExcelで使えるテンプレートがWeb上で配布されているので、それらを活用するのも良いでしょう。イメージに近いフォーマットが見つかれば、白紙の状態から自身で作るよりも、大幅に時間が短縮できます。
手順⑥業務マニュアルを運用・改善する
ある程度内容が完成したら、業務マニュアルを仮運用しましょう。そして、仮運用前に担当者に目を通してもらうことも大切です。その時点で情報の抜け漏れがないか確認し、早めに修正しておくことで後から大幅に修正する必要がなくなります。
仮運用時も担当者にチェックしてもらったからと安心せず、何か問題が起きていたり、わかりにくかったりするところがないかを周囲に確認しましょう。
仮運用が終わったら、その中で得られた改善点や修正点を反映していきます。反映した後は、リリースして問題ないかを担当者にレビューしてもらいましょう。
わかりやすい業務マニュアルを作る人がやっていること
ここからは、さらに読みやすく活用されやすい業務マニュアルを作るためのコツを8つご紹介します。
作業の全体像を掴む
わかりやすい業務マニュアルを作るためには、まず業務の全体像を把握することが大切です。
全体像を掴んでいない状態で部分的に説明をすると、全体で見たときに整合性の取れない内容になってしまう可能性があります。
全体像を把握できないとマニュアルを読む人も混乱してしまい、理解がしにくい状態となります。結果として、活用されないマニュアルになってしまうかもしれません。
作業手順の中の一部分にいきなりフォーカスするのではなく、まずは全体の流れに焦点をあて、その上で手順を説明していきます。その中で一つ一つの手順において、注意する点や具体的なやり方などを挙げていくと、わかりやすい業務マニュアルができます。
さらに業務マニュアルの冒頭に目次をつけて全体像を記しておくと、読み手も業務の流れをイメージできるようになり、各工程を理解しやすくなります。目次があれば確認したい箇所だけを閲覧できるので、特定の業務工程を見なおす場合にも便利です。
5W1Hを意識する
業務マニュアルや手順書に限らず、人に伝わる文章を書くときは「5W1H」を意識することが大切です。
「いつ」「どこで」「誰が」「なにを」「なぜ」「どうやって」をわかりやすく記載することで、誰が見てもわかりやすい文章になります。5W1Hを意識することで、マニュアル化する業務の対象や範囲も明確になります。
たとえば来店した顧客にDMを送付する業務の場合、ただ単に「顧客にDMを送る」とマニュアルに記載するだけでは、現場にはなかなか定着しないことが予想できます。「顧客にDMを送る」という一文だけの場合、そもそも誰が行うのかも明確になっていません。
初回の接客をした営業担当が送るのか、社内で担当を振り分けるのかといったように、「誰が」を決めておく必要があります。そのほか、「いつ」は来店から何日後に送るのか、「どうやって」はどのツールで送るのかなどを明確にしておきましょう。
そのうえで、なぜそれを行う必要があるのかを明記することによって、従業員が業務マニュアルを遵守徹底する可能性が高まります。
特に手間のかかる業務の場合、それを行う理由がわからなかったり、やる必要性を感じなかったりすると、実行しない従業員も出てきます。手順どおりにその業務を行うことによってどのような効果があるのか、行わなければどのようなリスクがあるのかなどを示しておくと良いでしょう。
5W1Hをしっかりとマニュアルに盛り込むには、それらを記載する欄をフォーマットに設けることもひとつの方法です。フォーマットを活用すると書き忘れが防げるほか、マニュアルを読む従業員にとっても、概要が一目で分かりやすいというメリットがあります。これによって、より伝わりやすい業務マニュアルになるでしょう。
考え方と行動を分ける
業務マニュアルを作る際は考え方と行動を明確に分けて記載しましょう。
たとえば「考え方」とは判断基準や行動指針などです。 一方の「行動」とは具体的にやるべきことで、手順・量・回数などを明確に記載します。
「行動」として書かれた内容は、業務マニュアル通りに進めれば誰が実施しても同じような結果になることが想定されます。反対に「考え方」は人によって違うので、本人はマニュアル通りに動いたつもりでも、同じ結果にはならないことが多々あるのです。
仕事を円滑に進めるためには考え方も大切ですが、業務マニュアルとして大事なのは、誰が実施しても同じ品質になるようにすることです。
そのため、考え方と行動は明確に分けて、やるべきことを具体的に書きましょう。
作業内容を担当者別や時系列で整理する
業務業務マニュアルには、工程をそのまま並べるだけではなく「この作業では何に気をつければ良いか」といった注意点やポイントを、手順ごとに解説しましょう。
また過去の失敗事例などから、注意すべき点などをあらかじめ業務マニュアルで提示しておくと、同じミスを回避しやすくなるでしょう。
基準を明確化する(作業時間・合否・チェックポイントなど)
業務マニュアルでは基準を明確に示しておくことが重要です。「長時間」「すぐに」のような、人によって捉え方の異なる言葉を使うのは避けましょう。量や時間などは数字で示します。
また、チェックポイントや合否を見極めるポイントも、感覚的なものではなく、明確な基準を定めておきましょう。
図やイラストを活用する
文章のみの業務マニュアルはどうしても単調で、理解するのに時間がかかりやすくなります。そのため、必要に応じて画像やイラスト、図解を取り入れながらマニュアルを作成することを心がけましょう。
特に「どのくらいまで火を通せば良いのか」「トッピングはお皿のどこに置けば良いのか」など視覚的に伝えないとわかりにくい業務は、画像や動画を使うのが上手なマニュアル作成のコツです。
そのほか、全体的な業務の流れを文章だけではなくフローチャートで示したり、店舗内をエリア別に担当する場合はフロアマップを載せたりなど、図やイラストがあるほうが理解が進みやすい場面は多々あります。
わかりやすい業務マニュアルは読む時間を短縮できるので、その分、業務に集中できます。また文章だけの説明と比べると、図やイラストがある方が個人による解釈の違いが生まれにくくなります。内容が正確に伝わることによって仕事の質が上がることも期待できるでしょう。
テンプレートを活用する
分かりやすい業務マニュアルを作るには、テンプレートを活用するのもひとつの方法です。
業務マニュアルに記載する内容は各企業によって異なりますが、記載するフォーマット(書式)は、必ずしもオリジナルである必要はないのです。テンプレートを活用すればゼロから作る時間を省けます。
さらに、見やすいフォーマットを利用すれば、それをもとに作成したマニュアルも分かりやすくなることが期待できます。
業務マニュアルを運用するコツ
前の章では業務マニュアルを作成するコツをお伝えしましたが、マニュアルは作って終わりではありません。しっかりと運用することで、意味のあるものになります。
業務マニュアルを運用する際のコツは、定期的に内容を見直すことや、いつでも閲覧できるようにすること、 共有しやすい形式にすることなどが挙げられます。
定期的に内容の見直しを行う
業務マニュアルや手順書は一度完成したからといって、それで終わりではありません。実際に業務の中で活用していくうちに、改善点や修正箇所が見つかるケースも少なくないからです。
また、新たな手順が追加されたり、既存のやり方が見直されたりしたときは都度更新することが大切です。必ず担当者を決めて、業務手順が変わった際には業務マニュアルも更新するように徹底しましょう。
たとえば現場でトラブルやクレームがあった場合には、その対策を検討し、すぐに業務マニュアルに盛り込むことが重要です。従業員への注意事項も個人へ口頭で伝えるだけでは、その場限りで終わってしまいます。
しかし、業務マニュアルに反映させておけば、注意を受けた本人は都度マニュアルを見ながらチェックすることにより、抜け漏れを防げます。さらに他の従業員にも同じ内容を伝えられるので、ミスを未然に防ぐことができます。
また、業務マニュアルを見直すのはトラブルがあったときだけではありません。売上が好調な店舗があれば、なぜ成功しているのかを分析し、他の店舗や部署でも応用できるようにマニュアルに記載しておきましょう。
業務マニュアルを好きなときに閲覧できるようにする
業務マニュアルの内容を現場に定着させるためには、各担当者が必要なときに閲覧できる状態にしておくことが重要です。
何か不明点が発生した場合に、業務マニュアルを見てやり方を確認できれば、社内統一のルールや考え方が身につく上に、決められた手順にそって進めることができます。
一方、業務マニュアルをすぐに見られる状態になければ、各々が自分の判断で進めてしまうかもしれません。そうなると、せっかく作ったマニュアルの内容も現場に反映されなくなってしまいます。
たとえば飲食店の厨房で働いているけれども、業務マニュアルは事務所に保管しているといった状態です。反対に、必要なときに閲覧できる状態とは、どの従業員でもアクセスできる場所や、実際に働く現場の近くにある状態を指します。
ただし、部外者でも見られる位置に保管するのは、守秘義務やセキュリティ上よくありません。従業員だけがすぐに開ける場所に置いておくのが理想です。 たとえばクラウド上に保管しておき、スタッフだけが知っているパスワードをかけるなどもひとつの手段です。
更新・共有しやすいツールを利用する
各自が好きなときに業務マニュアルを閲覧できるようにするには、共有しやすいツールを使うのも重要なポイントです。
前述したように、業務マニュアルのデータをクラウド上で保管するのも良いでしょう。また関係者だけがアクセスできるマニュアル用のサイトを作ったり、アプリ上で共有したりするのも方法のひとつです。
反対に、共有しにくいツールは紙のマニュアルです。 紙に印刷されたアナログのマニュアルは、現物を保管している場所でしか閲覧できません。現場と保管場所が離れている場合や、リモートワークで自宅にいる場合は確認できなくなってしまいます。
さらに、マニュアル運用においては更新しやすいツールであることも重要です。作業手順が変わった場合などに、随時マニュアルを更新する必要があります。
もし紙に印刷したアナログのマニュアルであれば、内容の修正も印刷も大変に感じ、更新自体が滞ってしまうことにもなりかねません。手軽に修正し、すぐに共有できるツールを選びましょう。
業務マニュアルを作成できるツール
ここまでは、業務マニュアルの作成や運用のコツをお伝えしました。ここからは、実際に業務マニュアルを作るときに使うツールを紹介します。
パワーポイント・Googleスライド
パワーポイントやGoogleスライドは、プレゼンテーションのスライドを作るツールです。
図やイラスト、画像、表などを貼れるため、デザインを多用するマニュアルを作るときに向いています。文字もデザインも自由にレイアウトでき、 視覚的に分かりやすい資料を作れます。
Word・Googleドキュメント
WordやGoogleドキュメントは書類を作成するツールです。図や画像が少なく、文章が多いマニュアルにはWordが向いています。ページ割を指定できたり、見出しや目次を設定したりできる点が便利です。
ただし、Excelのような表計算はできないため、数字を多用するマニュアルには向いていません。
Excel・Googleスプレッドシート
Excel・Googleスプレッドシートは表計算ができるツールです。帳簿のように数字をたくさん使うマニュアルに向いています。グラフを作成することも可能です。
Excel・Googleスプレッドシートならではの特徴は、1つのファイルの中にシートをいくつも作れる点です。内容別にシートを分けるなど、活用方法は幅広くあります。
ただし、画像や文字のレイアウトはパワーポイントほど自由にできないため、デザイン重視のマニュアルには向いていません。
動画
動画は、画像・イラストや文章だけでは分かりにくいことを伝える際に向いています。
たとえば飲食店の調理方法や、接客する際の話し方などは、動画のほうがわかりやすいでしょう。
動画を用いた業務マニュアルは、近年増えつつある形式です。動画データを用意し、アプリやクラウド上などで共有します。
📚関連記事を読む
わかりやすい業務マニュアルの作成・閲覧なら「はたLuck®︎」
業務マニュアルの作り方や効果について解説しましたが、せっかく質の高いマニュアルを作成しても、適切に活用されなければ意味がありません。
作成したマニュアルをいつでもどこでも確認できるようにするのが「はたLuck®︎」です。
はたLuckサービス概要資料、導入事例集

店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。
ここからは、「はたLuck®︎」を活用して得られる主なメリットについて解説します。
好きなときに業務マニュアルを確認できる

「はたLuck®︎」では「マニュアル」機能を搭載しています。管理画面からマニュアルを投稿すれば、従業員一人ひとりが自分のスマートフォンから好きなタイミングで確認することができます。わざわざ紙のマニュアルを確認したり誰かに聞いたりする手間が省けるほか、困ったときにすぐ手元のアプリからマニュアルを確認することで、疑問を解消できるのも魅力でしょう。
また、いつでもすぐに確認できることは、マニュアルの内容を周知徹底する上でも重要なポイントです。現場から離れた場所にマニュアルが置かれ、必要なときに閲覧できない状態の場合、マニュアルの存在自体を忘れてしまうこともあります。
その点、スマートフォンから確認できるなら、各従業員の一番近くにあるといっても過言ではなく、現場にも定着しやすいでしょう。
教育コストの削減が図れる
「はたLuck®︎」の「マニュアル」機能を効果的に活用することで、新入社員が各自で予習・復習を行えるので、教育係である上司・先輩が直接指導する手間を最小限に抑えることが可能です。OJTにかかる時間を短縮でき、新入社員や中途社員が入った際の教育コストを削減できます。マニュアルを確認したかどうかをチェックできる機能もあるので、マニュアルの周知徹底も簡単に行うことができます。
また、マニュアルを共有できるのは同一の店舗内に限りません。たとえば全国展開しているようなお店であっても、「はたLuck®︎」の「マニュアル」機能を使えば、日本中の全店舗で同じマニュアルを見ることができるのです。
これにより、各店舗で個別にマニュアルを更新したり、教育したりする手間を減らせます。ほかの店舗スタッフによる知見やノウハウをマニュアルで共有できることも、教育コストの削減につながるでしょう。
動画や画像を使って手順を視覚化できる
「はたLuck®︎」を使えば動画や画像を使って、より手順をわかりやすく視覚化できます。どうしても文章だけだと伝わりづらいことも多く、動画や画像を効果的に用いてマニュアル共有ができるのは大きな強みです。
説明の内容が複雑になると、文章から読み取れる意図や解釈の仕方は、個人によって違いが出てしまいます。また細かな作業のポイントなど、人によってはイメージしづらい場合もあるでしょう。そのような場合にも、動画や画像で視覚的に伝えることによって、認識の違いをなくすことができます。
それにより品質のバラつきを抑えられるため、結果的にクレームなどを回避することにもつながるでしょう。特に動画は紙のマニュアルでは共有できないため、アプリを活用する「はたLuck®︎」ならではのメリットといえます。
「はたLuck®︎」の「マニュアル」機能の活用事例と実際に届いた声
大手外食チェーンストア「大戸屋ごはん処」を運営する株式会社大戸屋様は、本部と店舗間のコミュニケーションの効率化を測るために国内一部128店舗に「はたLuck®︎」を導入しました。
従来、各店舗1台のみの管理用パソコンを介してマニュアルを提供していました。しかし、「はたLuck®︎」を導入したことで、スタッフ一人ひとりにアプリを介して適切にマニュアルを届けることが可能となり、教育コストの軽減につながりました。
また、「はたLuck®︎」を導入したことでスマホから場所や時間を問わず情報を確認できるようになったことは、社内で大きく評価されています。
本部からも
「管理画面からマニュアルをアップするだけなので店舗への情報発信が簡単」
「動画も格納できるため、画像だけでは伝わりづらかった調理方法もわかりやすくなり、外国人スタッフにも伝わりやすくなった」
などの声が多数届いており、業務効率化にも貢献しています。
業務マニュアルの共有にお困りの際には「はたLuck®︎」にお任せ
質の高いマニュアルを効率よく作成し、社内で使いやすくするためにツールの活用を検討するのもひとつの手です。
店舗マネジメントツール「はたLuck®︎」は、実際に働いている従業員やスタッフのスマホに専用のアプリを入れることで、簡単にマニュアルの共有ができます。
マニュアル共有について悩んでいる方はぜひ、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。
はたLuckサービス概要資料、導入事例集

店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。

店舗DXコラム編集部
HATALUCKマーケティンググループのスタッフが、記事の企画・執筆・編集を行なっています。店舗や施設を運営する方々向けにシフト作成負担の軽減やコミュニケーション改善、エンゲージメント向上を目的としたDXノウハウや業界の最新情報をお届けします。