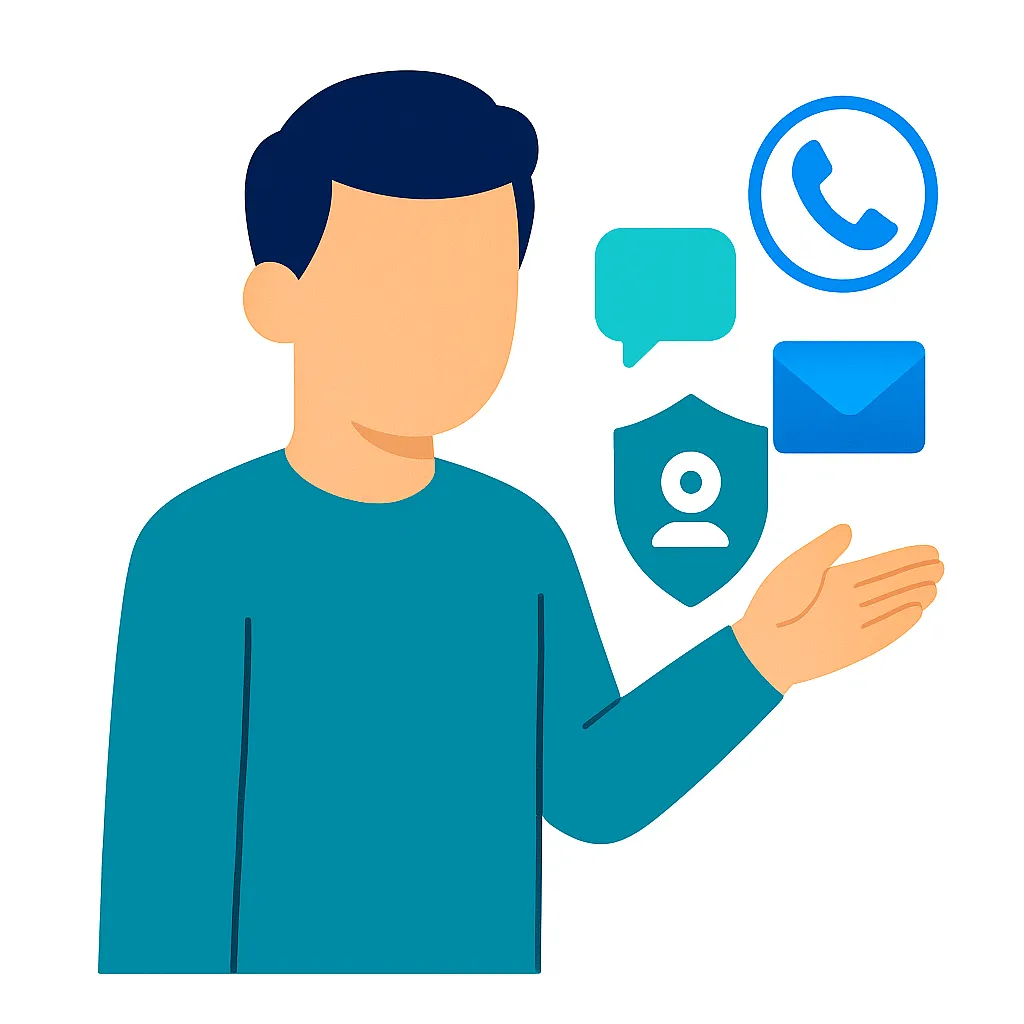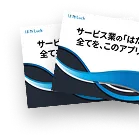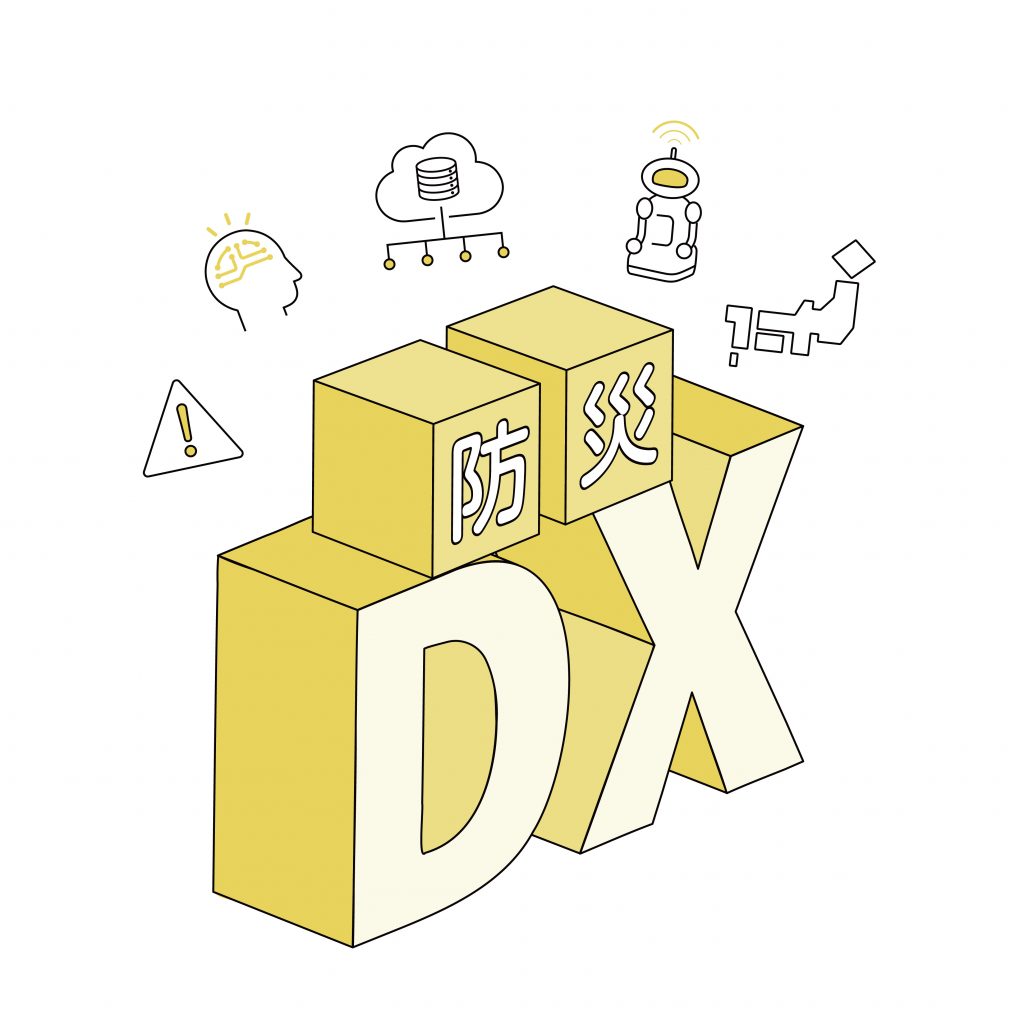
毎年のように大きな自然災害が起こる日本。いつどこで発生するかの予測は困難であり、日頃の備えが推奨されています。企業においても、社会的な責任を果たすために、防災対策に努めなければなりません。
特にサービス業は消費者の生活に寄りそう業態であることから、従業員や顧客の安全確保はもちろん、業務の継続性も求められます。これには従来の避難計画より踏み込んだ事業全体を組み込んだ防災計画の策定が必要となっていきます。そこで注目されているのが「防災DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。
本記事では、防災DXの基本的な概念を解説するとともに、サービス業における重要性や導入のメリットについてご紹介します。DXを活用した災害対策のトレンドを理解し、実践的な防災対策を検討してみましょう。
目次
防災DXとは
防災DXに関して、基本的な定義や求められるようになった背景、従来の防災対策との違いを把握しておきましょう。
防災DXの定義
近年、大企業だけでなく、中小企業でも積極的に導入されているDX(デジタルトランスフォーメーション)は、ICTなどのデジタル技術を活用し、業務プロセスを効率化しながら新たな価値を生み出す取り組みです。
このDXの概念を防災や減災に適用するのが「防災DX」です。災害時の迅速な対応や、被害を最小限に抑えるためにデジタル技術を活用することを指します。さらに、復旧・復興を支援するシステムも含まれ、自治体や企業が縦割りで管理していた防災データを統合・連携することで、より効果的な防災対策が可能になります。
防災DXを導入することで、住民や従業員の安全確保、迅速な情報共有、業務の継続性向上など、多くのメリットが期待できます。
防災DXが求められる背景
昨今、自然災害が激甚化・頻発化しており、経験したことのない豪雨や高い気温などを体験した方も多いでしょう。気候変動による気象災害のリスクが向上しており、豪雨による水害や土砂災害、高温による熱中症などは、さらに増えることも予想されています。
また、東日本大震災や能登半島地震では、想定外の規模の被害が発生しており、従来型の防災対策では限界があることは明らかです。さらには人口減少や高齢化などの社会状況も織り込んだ防災対策が欠かせない状況になっています。
そのため、IoTなどのデジタル技術を防災対策に活用し、災害発生前の予測はもちろん、復旧・復興へ向けた動きを加速させ、被災地に貢献することが求められています。すでに能登半島地震が発生した地域では、実際に避難所データの集約や避難者情報の把握がデジタルで行われるなど、少しずつ災害現場での導入も始まっています。
従来の防災対策との違い
従来の防災対策は紙ベースで行われていることが多く、災害時にすぐに参照しづらいという問題がありました。また、紙ベースでは即時に連絡できず、最新情報が更新されにくかったり、紛失してしまったりするという欠点もあります。現場での意思決定が遅れるとともに、決定の通知も遅れるといったリスクも内包しています。
防災DX導入により、クラウド型の防災システムやスマートフォンアプリが活用することで、即時に情報発信でき、リアルタイムの情報が共有されやすくなります。また、自動アラートを発信することもできるので、迅速な対応が可能です。
過去のデータや、従来は縦割りだった自治体や企業間でのデータを連携させることにより、危険度の予測や被害状況の即時共有なども図れます。こうした予測や情報の共有は、仮に被災してしまったとしても、復旧・復興への大きな足掛かりになっていきます。
防災DXが企業に与える影響
近年、防災DXに積極的に取り組む企業も少しずつ増えています。ここからは防災DXが企業に与える影響について見ていきましょう。

事業継続性(BCP:事業継続計画)の強化
防災DXを導入することにより、業務継続計画(BCP)を強化できるようになります。
例えば、クラウド型の防災情報管理システムやAIを活用した災害予測システムなどを導入すると、災害時のリスクを事前に把握できるようになるため、リスクに応じた対策を講じやすくなるでしょう。
また、被災した場合でも、リアルタイムで従業員の安否確認が取れたり、周辺情報の集約が行えたりするようになります。復旧までの時間を早めることができるため、長期的な事業停止リスクを最小限に抑えることができます。
人的被害・経済的損失の低減
AIやIoTを活用することで、災害発生時でも早い時期から警戒が可能になります。従業員や顧客の安全確保という基本的な防災対策を取りやすくなるでしょう。
また、被害状況をリアルタイムで把握できるため、適切な対応を取りやすくなります。近隣の店舗と連携した対応を取っていくことも可能です。業務停止やサプライチェーンの混乱を防ぐことで、経済的損失のリスクも減らせるでしょう。
ステークホルダーへの信頼向上
防災DXの積極的な導入により、従業員、取引先、顧客からの信頼を得られるようになります。
適切な防災対策が取られているということは、企業の社会的責任(CSR)やESG経営の観点で株主や投資家からの評価につながり、企業価値の向上につながります。
顧客や従業員に対する安心感も提供できるため、顧客満足度や従業員満足度の点からも、防災DXは見逃せない取り組みでしょう。
サービス業における防災DXの重要性
サービス業は他の事業と比べ、顧客との接点が多いという特徴があります。そのため、防災の観点では、従業員はもちろん、顧客の安全確保も欠かせません。
その点、防災DXを導入すると、顧客や従業員への安全性を高めることができ、事業継続性も高めることができます。ここではサービス業における防災DXの重要性を確認していきます。
サービス業が直面する防災リスク
同じサービス業でも、業種によって変わってくる防災上のリスクについて見ていきましょう。
小売・飲食業における災害時の混乱
地震や台風、豪雨などの災害が発生すると、店舗の棚崩れや停電、浸水などの被害のほか、物流が寸断されることが考えられます。
スーパーやコンビニなどの小売業においては、近隣の顧客による買いだめ需要が高まる一方で、停電や故障によってレジが使えず、売上金や在庫の管理に支障が出ます。販売している情報が口コミやSNSによって広まると、1つの店舗に顧客が集中し、混雑も発生する可能性も否定できません。
また、飲食店では、ガスや水道の供給が止まることで、営業も止めざるを得ません。食材の廃棄が増えてしまうほか、浸水被害による店舗の清掃などの手間も発生することがあります。
ホテル・宿泊業の避難対応
ホテル・宿泊業においては、夜間・就寝中にも顧客の安全を確保しなければならないという他の業種にはない特徴があります。地震や火災など突発的な災害が発生した場合にも、多くの宿泊客を安全に避難させる必要があるため、避難マニュアルの整備などすでに十分な災害対策を行なっている宿泊施設は多いでしょう。
しかし、近年、インバウンド需要が高まる中で、防災面においても多言語対応によるスムーズな情報提供をすることが求められています。
停電による設備の機能停止や、食事・飲料の提供が滞ることで、宿泊客の不満が高まりやすくなります。こうした事態を防ぐためには、自家発電設備の整備、避難マニュアルのデジタル化が求められます。
防災DXによるリスク低減の具体例
防災DXを導入することで、さまざまなリスクを低減させることができます。サービス業における具体的な防災DX事例を確認していきましょう。
AI・IoTを活用した防災システム
ビッグデータとAIを活用した災害予測システムを活用することで、気象データや過去の災害情報が分析でき、事前に細やかなリスクを把握できるようになります。
また、IoTによるセンサーを店舗や施設に導入することで、温度計や浸水センサーが異常を感知し、リアルタイムに通知されるようにすることも可能です。停電時や水害時の対策を速やかに取れるようになるでしょう。
クラウドを活用したBCP管理
クラウドを活用することで、災害や何らかの障害が発生した場合に、事業活動が中断されないようにするBCP管理もできます。
例えば、リアルタイムに報告できるクラウド型のプラットフォームを導入すると、従業員の安否確認、避難指示、店舗・施設の被害状況を一元管理できます。また、小売業においては、全国の店舗情報をクラウド上で統合し、被災地の在庫状況をリアルタイムで把握できるようにするなどが考えられます。こうした情報があれば、災害時でも他店舗から物資を供給するなどの対策を取れるようになるでしょう。
スマートフォンアプリを活用した安否確認
災害発生時には、従業員や顧客に素早く情報提供を行う必要があります。
従業員とのやり取りができるアプリを導入することで、重要な連絡を直接従業員のスマホへ送ることができます。災害時に自動で通知が送られる安否確認アプリを導入すると、迅速な安否確認を取ることができ、BCP管理にもつながります。
また、多言語対応のアプリを活用すると、日本人だけでなく外国人の顧客に対しても的確な避難誘導や情報発信を実施できるでしょう。
防災DXの導入メリット
サービス業において、防災DXを導入した場合のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。一つずつ見ていきましょう。
人的ミス削減
防災DXを導入することで、手作業や紙ベースにより発生しやすいミスを減らし、素早く正確な対応ができるようになります。デジタルマニュアルの活用によって、事務所へたどり着けない場合でも、手元にあるPCやスマホで最新の避難情報や店舗の運用方針を確認できるようになります。
また、安否確認においても、管理者が漏れのない情報を素早く集約できます。
効率化
情報の収集や共有がスムーズになるため、業務が効率的になります。
クラウド型の防災システムを活用すれば、複数店舗の情報をリアルタイムで確認でき、適切な指示を出せるようになります。被害のない地域からの物資の供給のほか、人的な応援も出しやすくなるでしょう。
専用の防災アプリ以外でも、スマホでメッセージをやり取りできるツールであれば、効率的な安否確認、被害報告、対応の指示をリアルタイムで行えます。
コスト削減
IoTセンサーの活用によって、店舗や施設内の異常アラートがリアルタイムに検知できるようになり、災害による被害を最小限に抑えることができるようになります。これにより、復旧にかかる費用の負担も軽減できるでしょう。
また、防災DXによって従業員満足度が向上することは、従業員の心理的安全にもつながり、離職防止にも効果的です。長期的には採用コストの削減にも寄与します。
安全性向上
AIやIoTを活用した災害予測や、リアルタイムの避難誘導システムは、災害時のリスクを事前に察知し、迅速な対応を取るために有効な手段です。また、避難マニュアルのデジタル化により、誰でも簡単に避難方法を理解できるようにもなっていき、安全性の向上に役立ちます。
企業の信頼性向上
防災DXに積極的に取り組む姿勢が、従業員や顧客に対する安全配慮であると評価されると、企業のブランドイメージが向上します。その結果、取引先や投資家からの信頼を得やすくなるでしょう。
また、BCP強化にもつながり、ESG経営の一環としても評価され、企業価値の向上が見込まれます。防災DXに取り組む姿勢を積極的に発信していきましょう。
防災DXの導入ステップ
防災DXを効果的に導入するには、計画策定からツール選定、運用・改善の3ステップを確実に進めることが重要です。一度導入すれば終わりではなく、実際の運用を通じて、継続的に地域や店舗に合わせ改善していくことで、より実効性のある防災体制となっていきます。
防災DXの計画策定
まずは、従来の防災計画における課題を明確にする必要があります。防災DXを導入することで、どのような解決策が図られるのかといった検討を経てから、計画を策定するようにしましょう。
現状の課題には、安否確認の遅れ、避難誘導の混乱などか考えられます。それに対し、DXを導入することで、現場も本部も短時間で従業員の状況を確認できたり、リアルタイムの情報を反映した避難誘導ができたりするようになっていきます。
また、計画には、具体的な導入スケジュールの策定も必要です。システムを導入する時期や、実際の防災訓練にてテスト運用する時期の検討も同時に行うようにしましょう。
適切なツール・システムの選定
防災DXには、計画に対応したツールやシステムを選定することが重要です。専用のツールではなくとも、スムーズにDX化を進めていくことができます。
例えば、安否確認には社内チャットやメールを一斉送信したり、クラウドストレージに避難マニュアルを共有したりすることが考えられます。また、被害状況の共有やIOTセンサーによる停電・高温対策は、被災後の復旧作業の負担を軽減できます。
まずはテスト運用できるツールを選定して試験運用したうえで、導入・運用のコストや負担を検討すると良いでしょう。
運用と継続的改善
防災DXに組み込むツールを選定したら、運用テストや防災訓練を実施することが重要です。実際に機能するか、操作性はどうかといった観点から検証を行いましょう。
特に、従業員のデジタルリテラシーに差がある場合は丁寧な導入と、フィードバックによる改善が必要です。防災DXを組み込んだ防災訓練と改善を継続的に行い、従業員に意識づけていきましょう。
防災DXを考えるなら「はたLuck」を活用しよう
はたLuckは、防災DXにも活用できる多機能アプリです。防災DXで利用できる機能と特徴をご紹介します。
重要な連絡を「お知らせ」機能で通知
はたLuckには「お知らせ(情報一斉配信)」機能が搭載されています。大きな施設であっても、働くすべての従業員の手元に、直接お知らせを配信することができます。天候の確認がしにくい大型店では、リアルタイムな気象情報や予測の配信が防災対策につながります。
業務連絡に使える「連絡ノート」
「連絡ノート」機能は、従来の事務所にあった紙ベースの掲示や連絡ノートの役割をデジタル化した機能です。店舗に行かずとも、はたLuck上で連絡事項を確認できます。
従業員が情報を確認したことを伝える「見ました」ボタンがついているので、安否確認ツールとしての利用も可能です。
「マニュアル管理」で緊急時の対策を共有
はたLuckには作成したマニュアルをいつでもどこでも確認できる「マニュアル」機能があります。各種業務マニュアルを掲載することが可能なので、防災計画や避難計画についても掲載できます。
従業員一人ひとりのスマートフォンからマニュアルを確認できるようになるため、好きなタイミングで見られる上に、マニュアルを確認したかどうかをチェックする機能も搭載されているため、現場にも定着しやすくなっています。
また、全店舗で同一のマニュアルを参照できるので、提供するサービスが標準化されるだけでなく、同じ基準に従った防災対策も可能になるでしょう。
「トーク」機能を活用して従業員とコミュニケーション
はたLuckの「トーク」機能は、いつでもどこでもリアルタイムにコミュニケーションをとることができる機能です。被災時の店舗の状況はもちろん、出勤していない従業員によって近隣の情報を共有してもらうことで、周辺エリアの状況を把握することができます。
個人的なメッセージアプリのアカウントを知る必要はなく、従業員のプライベートに干渉することなく、コミュニケーションを図ることが可能です。
防災DXへの投資は、企業の持続的な成長に不可欠
防災DXへの投資は、単なるリスク管理にとどまりません。激甚化していると言われる自然災害や、コロナ禍のような予期しない事態に対する備えは、将来にわたる競争力を支える基盤となっていきます。
はたLuckを活用することによって、新たなツールを採用せずとも、防災DXを導入することができるようになります。普段から利用しているはたLuckであれば、操作面で従業員が新たに学習することも少なく、負担軽減にもつながります。より効率的な防災対策を目指していきましょう。
はたLuckサービス概要資料、導入事例集

店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。

店舗DXコラム編集部
HATALUCKマーケティンググループのスタッフが、記事の企画・執筆・編集を行なっています。店舗や施設を運営する方々向けにシフト作成負担の軽減やコミュニケーション改善、エンゲージメント向上を目的としたDXノウハウや業界の最新情報をお届けします。