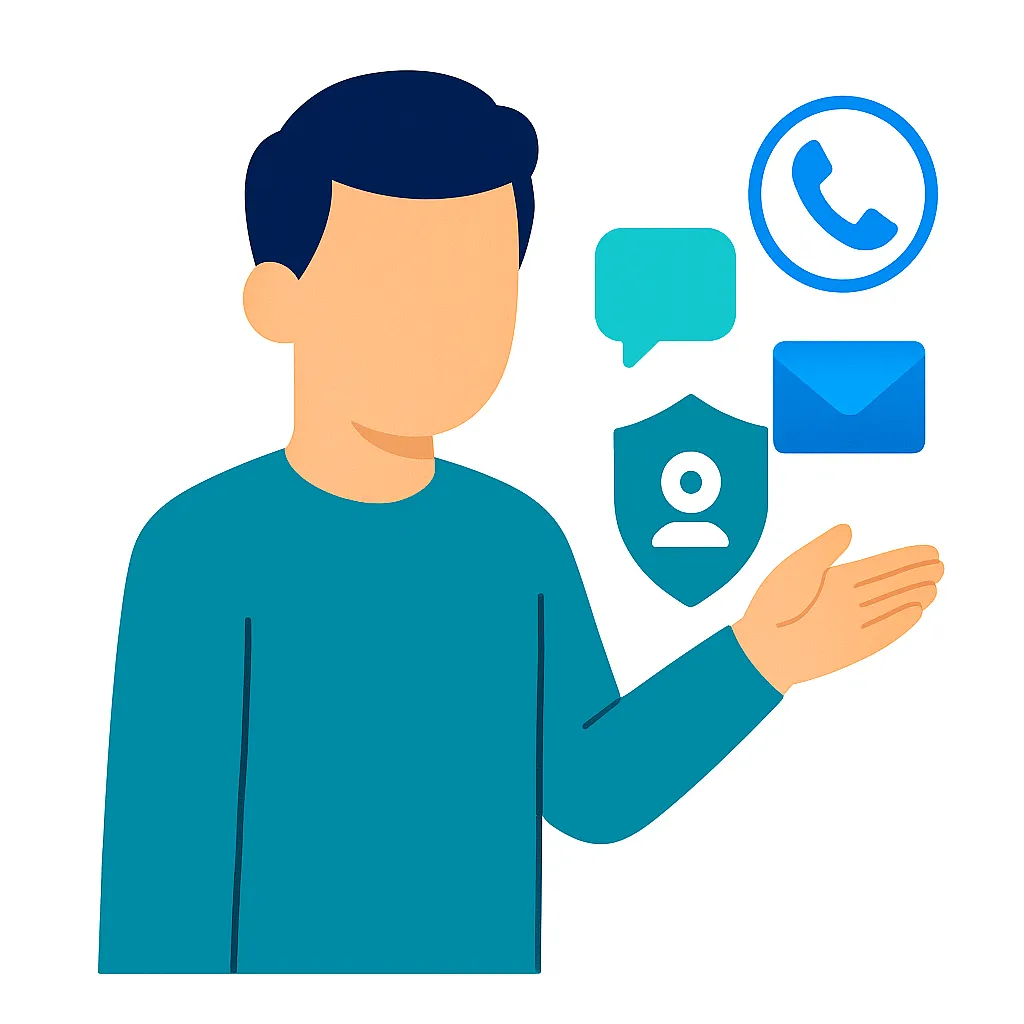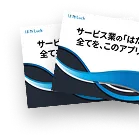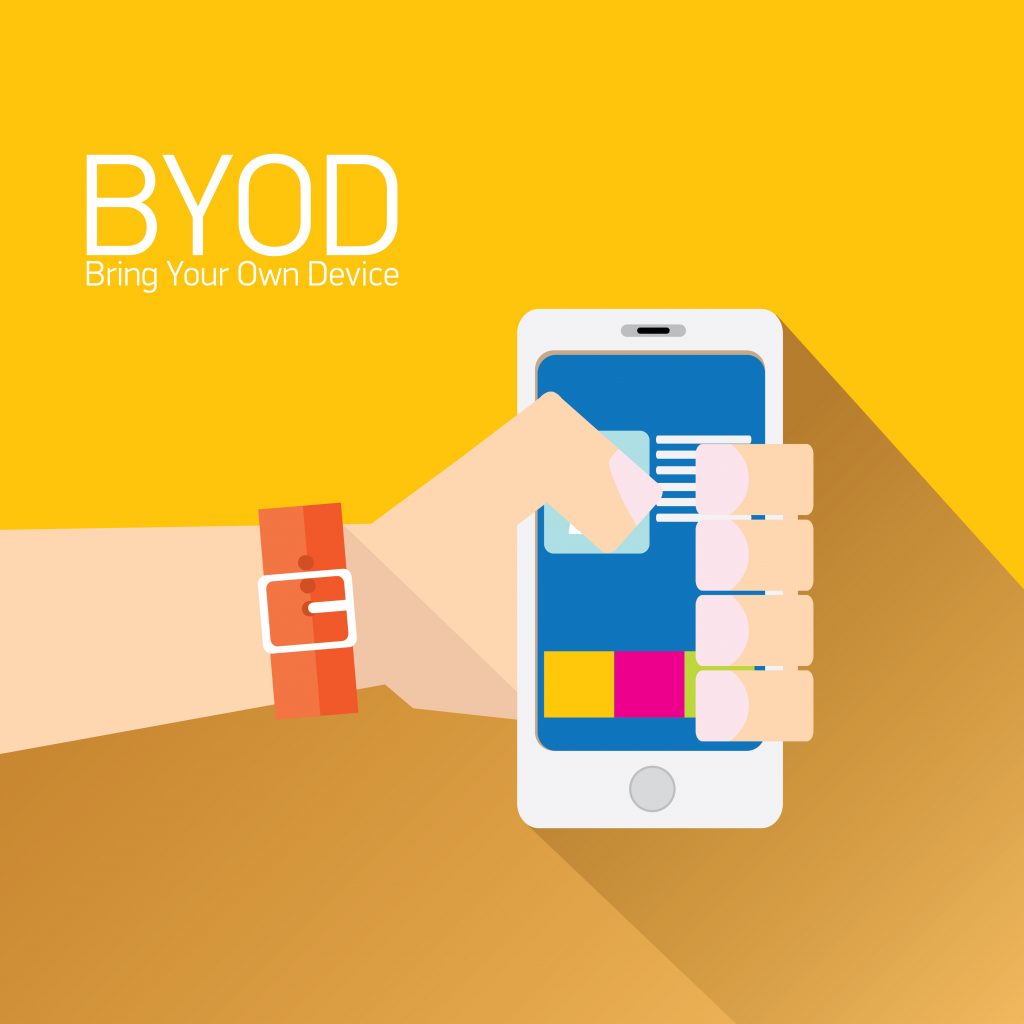
近年、企業の働き方改革やコスト削減の取り組みの一環として注目を集めているのが「BYOD」です。BYODを導入すると具体的にどのようなことが可能になるのでしょうか?本記事では、BYODの定義やメリット・デメリット、さらに導入時の注意点まで、網羅的に解説していきます。
目次
BYODとは?
BYODは「Bring Your Own Device」の略称で、従業員が個人所有しているデバイスを業務に使うことです。スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなど、さまざまな個人所有デバイスが対象となります。企業は従業員のデバイスを活用することで、コスト削減や業務効率化を図れるほか、従業員は使い慣れたデバイスで働けるため従業員満足度(ES)の向上も期待できるでしょう。近年のリモートワークの普及に伴い、BYODの導入を検討する企業は増加傾向にあります。
BYODの背景と普及の理由
BYODが普及した背景には、以下のような理由があります。
・スマートフォンなどのデバイスの高性能化
・クラウドサービスの増加
・テレワークなど柔軟な働き方への対応
このように、従業員のITスキル向上により、個人所有のデバイスでも十分に業務をこなせるようになりました。また、セキュリティ技術の進歩やモバイルアプリケーションの充実は、さまざまな業務をスマートフォンやタブレットで行えるようにし、BYODの実用性を高めています。
CYODとの違い
CYODは”Choose Your Own Device”の略で、企業が選定した複数の端末から従業員が選択する方式です。BYODでは端末の所有と管理責任は従業員となるものの、CYODでは企業が所有し管理します。CYODは企業のセキュリティ対策に沿った運用がしやすく、管理が容易です。
COPEとの違い
COPEは”Corporate Owned, Personally Enabled”の略で、企業が所有する端末を従業員に貸与し、一定の私的利用を認める方式です。COPEはBYODよりもセキュリティ対策が容易で、機密情報を扱う業務に適しています。
BYODのメリット
BYODの導入には、企業側と従業員側それぞれにメリットがあります。コスト削減から業務効率の向上までさまざまな利点がありますが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?企業側と従業員側のそれぞれについて見ていきましょう。
企業側
BYODを進めることで企業側が得られるメリットは以下の通りです。
端末購入・維持費の削減
BYODでは従業員が自身のデバイスを使用するため、企業は従業員全員分の端末を購入・管理する必要がなくなります。そのため、初期費用や維持費用といったコストを大幅に削減できるでしょう。また、端末の修理や保守にかかる費用も軽減されます。
従業員の満足度向上
従業員が使い慣れたデバイスを使用することで、新しいデバイスの操作を覚える手間や心理的負担がなくなり、業務への満足度が向上します。また、個人の好みに合わせたデバイスを選択できるので、従業員のモチベーションも上がるでしょう。
仕事とプライベートのデバイスを一元化できる利便性もあり、最新のデバイスを使用したい従業員のニーズにも応えられます。
業務効率化・生産性の向上
使い慣れたデバイスを使用することで業務効率が向上し、生産性が上がります。すでにデバイスの操作に慣れているため、新しいシステムの導入もスムーズに行えるでしょう。
個人の作業スタイルに合わせたカスタマイズも可能であるほか、モバイルデバイスの活用によって移動中や外出先での業務も容易になります。
リモートワーク環境の整備
個人デバイスを利用することで、リモートワーク環境の整備が容易になります。急な在宅勤務が必要となった場合にも柔軟に対応できるほか、場所を選ばない働き方の実現によってワークライフバランスの向上にもつながります。オフィススペースの削減にもつながり、コスト削減効果も期待できるでしょう。
シャドーIT対策
シャドーITとは、企業のIT部門が把握・管理していない個人や部門が独自に導入したITシステムやアプリケーションのことです。BYODの導入によって従業員が個人デバイスを業務に使用することが許可されるため、企業が把握していない非公式なアプリやサービスの使用を抑制できます。
📚関連記事を見る
従業員側
従業員側が得られるメリットは以下の通りです。
使い慣れた端末で業務ができる
個人のデバイスを使用することで、使い慣れた環境で業務を行えます。そのため、デバイスの操作に関する学習コストを削減できるほか、個人の好みに合わせたアプリやツールを活用できるでしょう。また、デバイスの切り替えによるストレスも軽減できます。
最新機種を利用しやすい
BYODが導入されることにより、個人の判断で最新のデバイスを購入・利用できます。新しい技術や機能をいち早く業務に活用できるほか、個人の興味や関心に応じて、最適なデバイスを選択可能です。
働き方を選択できる自由度が高まる
リモートワークやフレキシブルな働き方が可能になり、出張先や移動中でもスムーズに業務を行えます。個人の生活スタイルに合わせた働き方を選択できるほか、緊急時や突発的な業務にも柔軟に対応できるでしょう。
BYODのデメリット
BYODには多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。
企業側
企業側で想定されるデメリットは以下の通りです。
情報漏えいリスクの増加
BYODの導入により、個人デバイスからの情報漏えいリスクが高まるほか、紛失や盗難時のデータ保護が難しくなります。マルウェア感染のリスクが増加することや、従業員の退職時のデータ管理が複雑になる点に留意する必要があるでしょう。企業側でセキュリティ対策をしっかりと講じておくことも大切です。
セキュリティ対策の複雑化
多様なデバイスに対応するためのセキュリティ対策が複雑になることに加え、OSやアプリケーションの更新管理が難しくなります。また、個人デバイスへのセキュリティソフトの導入・管理を検討する必要があるほか、デバイスごとに異なるセキュリティ設定が必要になるケースもあるでしょう。
サポート体制の整備
個人デバイスのサポート体制を整える必要があり、多様なデバイスに対応できるIT担当者の育成が欠かせないでしょう。また、担当者育成に伴うサポートコストが増加する可能性がある点にも注意が必要です。
社内システムとの互換性の確保
多様なデバイスとの互換性を確保するための対応が必要です。場合によっては社内システムとの相性が悪く、アプリケーションの互換性テストが複雑化してしまうこともあるでしょう。デバイスごとの画面サイズや性能の違いに留意しながら作業を進めることが大切です。
従業員との間でのトラブル
私用と業務用の使用区分が曖昧になり、デバイスの使用に関するトラブルや責任問題が発生する可能性があります。また、デバイスの更新や交換のタイミングで意見の相違が生じることもあるでしょう。
従業員側
従業員側で想定されるデメリットは以下の通りです。
仕事とプライベートの切り替えが難しい
同じデバイスを仕事とプライベートで使用することで、切り替えが難しくなります。業務時間外でも仕事のメールやメッセージを確認してしまう恐れがあるほか、プライベートな情報と業務情報が混在するリスクがあります。
業務用とプライベートが分けられるような環境を整えられれば、両者の切り替えがつきやすくなるでしょう。
長時間労働になる可能性
仕事とプライベートの境界が曖昧になり、長時間労働になる可能性があります。いつでもどこでも仕事ができる環境となることで、過度の労働を招きかねません。
また、人によっては長時間のデバイス使用により、目の疲れや肩こりといった健康問題が生じるリスクがあるでしょう。
端末費・通信費の金銭的な負担
BYODの導入によって、個人がデバイスや通信費を負担することになります。場合によっては業務用のアプリケーションやクラウドサービスの利用料が発生することもあるでしょう。デバイスの故障や紛失時の修理・交換費用を個人で負担するのか、会社が一定額を負担するのか、社内できちんと取り決めをしておく必要があります。
BYODの導入に適した企業の特徴
BYODはすべての企業に適しているわけではありません。特に以下のような特徴を持つ企業では、BYOD導入によって大きなメリットを得られる可能性が高いため、自社が当てはまるか確認してみましょう。
リモートワークやハイブリッドワークを推進している企業
リモートワークやハイブリッドワーク環境を整備している企業では、BYODの導入が特に効果的です。
従業員が自宅やカフェなどさまざまな場所から業務を行う際、使い慣れた個人デバイスを活用することで作業効率が向上します。また、会社支給のデバイスを配布・管理する手間やコストを削減できるため、急な働き方の変更にも柔軟に対応可能です。
テレワークを前提とした勤務体系を採用している企業にとって、BYODは理想的な選択肢といえるでしょう。
ITツールを活用した業務が中心の企業
日常業務でクラウドサービスやウェブアプリケーションを多用する企業は、BYODとの相性が良好です。
現代のクラウドサービスはデバイスを選ばず利用できるため、個人所有のデバイスでも問題なく業務を遂行できます。特にG SuiteやMicrosoft 365などのクラウドベースの業務ツールを中心に使用している企業では、導入障壁が低く、スムーズに移行できるでしょう。
ブラウザベースのアプリケーションを中心に使用しているのであれば、OSの違いも大きな問題にはなりません。
従業員のデバイス利用率が高い企業
従業員の多くがすでにスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどのデバイスを所有・活用している企業では、BYODの導入がスムーズに進みやすいでしょう。
特に若手社員が多い企業や、ITリテラシーの高い人材が集まる企業では、個人デバイスの活用に対する抵抗感が少なく、導入によるメリットを最大化できます。従業員が日常的にデジタルツールを使いこなしている環境であれば、BYODへの移行もスムーズに進むでしょう。
セキュリティ対策が整っている企業
強固なセキュリティ基盤を持つ企業は、BYODのリスクを最小限に抑えながらメリットを享受できます。MDM(モバイルデバイス管理)ツールの導入やVPN環境の整備、多要素認証の実装など、適切なセキュリティ対策が整っていることがBYODの成功につながるでしょう。
また、定期的なセキュリティ教育を実施し、従業員の意識が高い企業では、情報漏えいなどのリスクを効果的に管理できます。セキュリティポリシーが明確で従業員に浸透している企業ほど、BYODの恩恵を安全に受けられるといえるでしょう。
コスト削減を重視する企業
端末購入費や保守管理費の削減を重視する企業では、BYODが有効な選択肢となります。特に成長過程のスタートアップや人員増加が見込まれる企業では、デバイス購入コストを抑制できるBYODが財務面で大きなメリットをもたらすでしょう。
また、デバイスの故障や更新に伴う管理コストも軽減できるため、IT予算の効率化を図りたい企業にとって魅力的な選択肢です。ただし、通信費の補助など一定の費用負担は発生するため、総合的なコスト分析を行った上で導入を検討することが欠かせません。
BYOD導入時の注意点
BYODの導入時には、いくつかの注意点があります。ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

制度設計
まず、BYODを導入するにあたって運用設計が欠かせません。運用設計を行う際には、以下の3つのポイントを意識するように心がけましょう。
明確なポリシー策定(利用範囲、責任分担、セキュリティ対策など)
BYODを導入する際は、利用範囲を明確に定義し文書化することが大切です。セキュリティ対策の最低要件を洗い出しておくほか、プライバシーポリシーを策定し個人情報の取り扱いを明確にしておくことも重要です。
導入対象デバイスの明確化
BYODの導入対象となるデバイスの種類を明確に定義しましょう。対応OSやバージョンの要件を明示するほか、必要なスペックや性能要件についても設定します。禁止デバイスや非推奨デバイスのリストも作成しておくと、よりわかりやすくなります。
情報セキュリティ対策の徹底
セキュリティの弱体化によって情報漏えいのリスクが高まるため、十分な対策を講じる必要があります。たとえば、以下の方法によってセキュリティを強化することが可能です。
・デバイスのパスワード設定を義務付ける
・リモートワイプ機能を導入する
・データを暗号化する
・VPNの使用を必須にする
さらに、以下の対策も重要です。
・MDM(モバイルデバイス管理)
・アクセス制御
・データ暗号化
・ウイルス対策ソフト
・認証強化
これらの対策を総合的に実施することで、BYOD環境のセキュリティリスクを軽減し、安全な業務環境を構築できます。
コスト負担の明確化
BYODを導入するということは、デバイスの購入を各人に任せることになります。そのため、購入費用や通信費の負担割合をどうするかを事前に決めておくことが大切です。アプリケーションやクラウドサービスの利用料負担を規定するほか、修理・交換時の費用負担ルールも設定しておきましょう。
運用・管理
運用・管理においても、以下のポイントを意識しておくことが求められます。
デバイス管理ツールの導入
セキュリティ対策などの目的として、必要に応じて端末管理ツールの導入を検討しましょう。具体的には、アプリケーションの配布・管理システムを整備するほか、デバイスの位置情報追跡システムを検討するといった策が有効です。
定期的なセキュリティ教育の実施
セキュリティポリシーを定期的に更新し、新たな脅威に対応したセキュリティ対策を導入することが重要です。セキュリティ監査を定期的に実施し、脆弱性を洗い出すことも忘れずに行いましょう。
また、インシデント対応計画を定期的に見直し、更新することで、不測の事態に備えることができます。
サポート体制の構築
BYODに関する定期的な研修を実施し、セキュリティ意識向上のためのe-ラーニングを提供することが重要です。情報漏えいについての研修を行うほか、最新のセキュリティ脅威に関する情報を定期的に共有し、社員のITリテラシーの向上等に努めましょう。
トラブル発生時の対応体制の整備
ヘルプデスクを設置し、トラブル発生時に迅速に対応できる体制を整えておくことも欠かせません。インシデント対応チームを組織し、緊急時に対応できる体制を準備するようにしましょう。定期的な訓練を実施し、対応力を向上させておくのもひとつの手です。
継続的な改善
BYODを最大限活用するためには、継続的に改善をしていくことが求められます。その際、以下の2つのポイントを考慮しながら進めていきましょう。
フィードバックの収集
デバイスの利用状況を定期的に分析するほか、アプリケーションの利用状況を把握し、最適化を図りましょう。その際、セキュリティインシデントの発生状況を確認し、適切に対策を講じる必要があります。なお、従業員に対して満足度調査を実施し、ユーザー目線の改善点を洗い出すことも重要です。
ポリシーや運用方法の見直し
技術の進歩や市場動向に合わせて、BYOD対応を定期的に見直すことも怠らないようにしましょう。従業員からのフィードバックを基に制度の改善を図るほか、法規制の変更に応じてポリシーの更新も必要です。
また、他社の成功事例や失敗事例を参考にすることで、自社のBYOD制度をより良いものにできます。
常に進化し続ける最新技術やトレンドに注目し、適切に導入することが大切です。昨今では、AIを活用した高精度な認証や全画面指紋認証などが登場しており、これらの最新技術はセキュリティ強化やユーザーの利便性も向上させるでしょう。企業がBYODを成功させるためには、こうした最新技術やトレンドを常に把握し、自社の環境に適したものを適切に取り入れていく必要があります。
BYODの活用事例
BYODは企業や自治体に導入が進んでおり、さまざまな成功事例が報告されています。ここでは、主に以下の3つの事例を紹介します。
ユナイテッドアローズ
ユナイテッドアローズは、国内外からの仕入れブランドやオリジナル企画の衣料などを販売するセレクトショップです。以前は、社員がモバイルデバイスを業務利用するには事前申請が必要であったため、外出時にはメールを確認するためにオフィスに戻らなければなりませんでした。
そこで、私物のスマートフォンを活用したBYODを導入。社員は外出先でも自分のスマートフォンを使って会社のメールやスケジュールにアクセスできるようになりました。結果として社員の移動時間の削減や業務効率の向上、また会社側もコスト削減につながっています。
コニカミノルタ
コニカミノルタは、プリンターやヘルスケア用機器などの製造・販売を行う電機メーカーです。BYOD導入の背景には、世界53カ国に拠点を持つグローバル企業として、社員の頻繁な出張に対応する必要があったことが挙げられます。
この課題に対応するために、「いつでもどこでもオフィス」を目指し、MDMツール導入をはじめとするセキュリティ対策も実施。その結果、出張の際でもスマートフォンがあればメールを確認できるなど、業務の効率化を実現しています。
大分県庁
大分県庁では、働き方改革の促進や業務の効率化を図るためにBYODを導入しました。導入にあたっては、MDMを利用してセキュリティを強化し、安全なリモートアクセス環境を構築しました。
これにより、職員は外出先や自宅からでも作業ができるため、希望者の多かったリモートワークを実現させることができたそうです。
BYODに関するよくある質問
BYODの導入を検討する際に、多くの企業が疑問や不安を抱えています。ここでは、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q. BYODとは何の略ですか?
BYODは「Bring Your Own Device(ブリング・ユア・オウン・デバイス)」の略称です。従業員が個人所有のスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどのデバイスを職場に持ち込み、業務に使用することを指します。従来の企業支給デバイスとは異なり、従業員自身が所有し、普段から使い慣れた端末を業務にも活用する働き方です。近年のモバイルデバイスの高性能化やクラウドサービスの普及に伴い、世界中の企業で採用が進んでいます。
Q. BYODを導入するメリットは何ですか?
BYODの主なメリットは、企業側と従業員側の双方にあります。
企業側では、デバイスの購入・維持費の削減、従業員満足度の向上、業務効率・生産性の向上、リモートワーク環境の整備などが挙げられます。
従業員側では、使い慣れた端末での業務が可能になる点、最新機種を利用しやすくなる点、働き方の自由度が高まる点などがメリットです。特に、デバイスの切り替えによるストレス軽減や、個人の好みに合わせたカスタマイズが可能になることで、業務への満足度向上につながるでしょう。
Q. BYODを導入する企業はどのような業種が多い?
BYODを積極的に導入している業種としては、IT・テクノロジー企業、コンサルティングファーム、広告・メディア関連企業、スタートアップ企業などが多く見られます。これらの業界は、デジタルツールへの親和性が高く、従業員のITリテラシーも比較的高いことが特徴です。
また、外勤の多い営業部門や、フレキシブルな働き方を推進する企業でも導入が進んでいます。最近では製造業や小売業、金融業などの従来型産業でも、働き方改革の一環としてBYODを導入する例が増えています。業種を問わず、リモートワークの普及とともに導入企業は拡大傾向にあります。
Q. BYODのセキュリティリスクを防ぐには?
BYODのセキュリティリスクを防ぐためには、複数の対策を組み合わせることが重要です。まず、MDM(モバイルデバイス管理)ツールを導入し、デバイスの管理・監視を行いましょう。
また、VPNの使用を必須とし、データを暗号化することで安全な通信環境を確保することも欠かせません。多要素認証の導入や、デバイスへのパスワード設定の義務付けも基本的な対策です。
紛失・盗難時に備えたリモートワイプ機能の実装や、業務データとプライベートデータを分離する仕組みも有効であるほか、定期的なセキュリティ教育を実施し、従業員の意識向上を図ることも不可欠です。
Q. BYODの導入にはどのような規則やルールが必要?
BYODを導入する際には、明確なポリシーやルールの策定が必須です。
具体的には、利用可能なデバイスの種類やOSバージョンの指定、必要なセキュリティ設定(パスワード、暗号化など)の基準、業務利用可能なアプリケーションの範囲などを定めます。また、費用負担の取り決め(デバイス購入費や通信費の補助範囲)や、プライバシーに関する方針(企業がデバイス内のどのデータにアクセスできるか)も明確にすべきです。
トラブル発生時の対応手順や、退職時のデータ削除プロセスなども規定しておくことで、導入後のトラブルを未然に防げるでしょう。
BYODを導入するなら「はたLuck」がおすすめ
BYODを導入するなら、「はたLuck」がおすすめです。ここでは「はたLuck」の主な機能について、見ていきましょう。
管理画面で個人の利用状況を確認できる
「はたLuck」では、店舗の投稿やシフトの状況などのアプリの各機能の利用状況を本部から確認できる仕組みとなっています。万が一、本部が把握しきれていない部分でトラブルが起きても、管理画面で確認することができるので、早い段階で解決が可能です。
情報の閲覧制限が可能
「はたLuck」の情報の閲覧は、IPによる制限がかけられます。閲覧するネットワーク環境を指定すれば、ネットワーク外からのアクセスを防げるでしょう。
またオプションとして、シフトに入っている時間しかマニュアルを閲覧できないといった制限が設けられています。移動中に開いたマニュアルを第三者によって勝手に見られてしまったり、デバイスを紛失してマニュアルが流出したりするリスクを最小限に抑えることが可能です。
利用していないスタッフや退職者の自動ログアウトや無効化もできる
「はたLuck」では、一定期間ログインしなかったユーザーは、自動的にログアウトされます。また、退職者などはアカウントの無効化を行うことで、はたLuckにログインできなくなります。これらの機能により、企業秘密の漏えいを防ぐことができるでしょう。
業務連絡は「連絡ノート」機能を活用できる
「はたLuck」の連絡ノート機能を活用すれば、従業員との情報共有が容易にできます。同機能を使えば、マニュアルの公開や更新などに関する情報も即座にスタッフへ共有することが可能です。
従業員はいつ・どこからでも連絡ノートを確認できるほか、「見ました」ボタンによる既読報告もできます。SVや店長が発信した情報を確認していない従業員の有無をチェックできるので、伝達漏れも防ぐことができるでしょう。
アプリに投稿された情報はダウンロードできない
「はたLuck」には、マニュアルの格納および閲覧機能がありますが、それを個人のデバイスにダウンロードし、保存することはできません。社内の重要な機密情報が外部に漏れてしまうリスクも低減できます。
スクリーンショット警告機能を搭載
「はたLuck」には、スマートフォンでスクリーンショットを撮影すると警告が表示され、画面保存ができない機能が備わっています。警告機能によって、情報漏えいのリスクを極力軽減することができます。
BYODを適切に導入して、業務効率化・生産性向上を図ろう
BYODは企業と従業員の双方にメリットをもたらす可能性がある一方で、適切な導入と運用が求められます。安全に進めていくには、従業員へ情報セキュリティの向上に関する研修を行うなどして、ITリテラシーを高めることも欠かせません。
また、企業と従業員の費用負担について明確に設定しておくことも大切です。双方が納得のいく形でBYODを導入できるよう、本記事を参考にして丁寧にプロジェクトを進めていきましょう。
はたLuckサービス概要資料、導入事例集

店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。

店舗DXコラム編集部
HATALUCKマーケティンググループのスタッフが、記事の企画・執筆・編集を行なっています。店舗や施設を運営する方々向けにシフト作成負担の軽減やコミュニケーション改善、エンゲージメント向上を目的としたDXノウハウや業界の最新情報をお届けします。