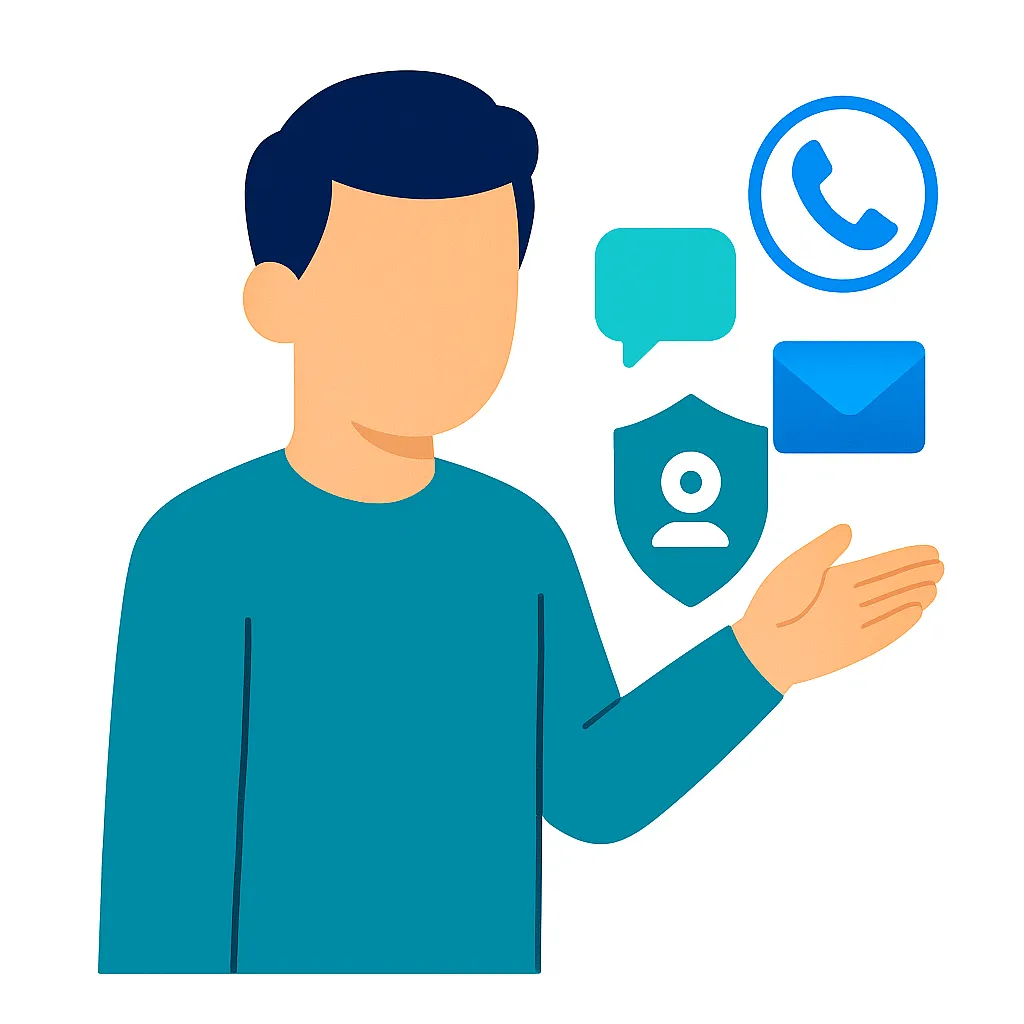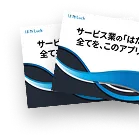ウェルビーイング(Well-being)とは?注目される背景や企業の取り組みを紹介
近年、ウェルビーイング(Well-being)を重視する動きが大きくなっています。ウェルビーイングとは、個人が肉体的、精神的、社会的に満たされて幸福を感じられる状態のことです。企業も、従業員のウェルビーイングのために施策を講じる必要性が高まっています。
とはいえ、「具体的に何をすればいいのかわからない」「取り組む必要性がわからない」といった人もいるのではないでしょうか。
ここでは、ウェルビーイングが広まった背景や企業が取り組むメリットと、具体的に何をすればいいのかについて解説していきます。
はたLuckサービス概要資料、導入事例集

店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。
目次
ウェルビーイングとは
ウェルビーイングとは、個人の権利や自己実現が保証されることによって、肉体的、精神的、社会的に満たされて幸福を感じられる状態にあることを指します。
企業は、就業面でのウェルビーイングを向上させるため、従業員の雇用条件の改善といった対応に加えて、働き方を選べる環境や、働きがいを感じられる環境を提供していくことを求められるのが昨今の状況です。
ウェルビーイングは、直訳すると「幸福」「健康」という意味です。世界保健機関(WHO)では、健康について下記のように定義しています。
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
公益社団法人日本WHO協会仮訳
健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。
また、厚生労働省では、
ウェルビーイングを「個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念」、就業面でのウェルビーイングの向上を「働き方を労働者が主体的に選択できる環境整備の推進・雇用条件の改善等を通じて、労働者がみずから望む生き方に沿った豊かで健康的な職業人生を送れるようになることにより、みずからの権利や自己実現が保障され、働きがいを持ち、身体的、精神的、社会的に良好な状態になること」
厚生労働省
と定義しています。
ウェルビーイングを構成する5つの要素
ウェルビーイングを高めるためには「PERMA」と呼ばれる5つの要素が大切だとする考え方があります。
ウェルビーイングを高めるために具体的に何をしなければいけないのかを考える際は、PERMAを意識してみましょう。
PERMA
- P(Positive emotion):ポジティブな感情
- E(Engagement):エンゲージメント
- R(Relationship):他者との良好な関係性
- M(Meaning):人生の意義、社会貢献
- A(Accomplishment):達成感
精神的に満たされた状態を指すウェルビーインクにおいて、ポジティブな感情を持つことは重要です。楽しい・嬉しいといった喜びを感じるだけではなく、やりがいや自己肯定感などにもつながります。
また、エンゲージメントは何かに没頭したり、積極的に取り組んだりする状態を指すもので、 モチベーションや生産性を高める要素のひとつとして欠かせません。
社会的な側面を充実させるために重要なのは、他者との良好な関係性です。ストレスの低減につながるほか、働きやすさも向上します。
さらに人生の意義や社会貢献、達成感といった要素も、自己実現や幸福感を覚える上で重要であり、これらを感じることで ウェルビーイングが高まります。
ウェルビーイングに関心が集まる理由

企業がウェルビーイングを意識するようになった背景には、さまざまなものがあると考えられます。
ここからは、ウェルビーイングが注目を集めている具体的な背景をご紹介します。
価値観の多様化
現代は宗教や人種、生まれ育った環境などが異なる様々な人が共存しているため、価値観も多様化しています。 何を良いと感じるかは人によって違い、これが幸せであるという完全な指標はありません。
そのため、個々人の価値観において心身ともに幸せを感じることが大切であり、より重要視されるようになってきています。この傾向は今後ますます強くなり、2030年にはウェルビーイングの考え方が世の中の前提になるとも言われています。
人手不足の深刻化
日本では労働人口が減少し、人材も流動化しているため、ますます人材を確保しづらい状況になっていくと見込まれます。こうした状況下で必要な人材を確保するためには、給与や福利厚生の充実に加え、働きやすい環境づくりや達成感を得られる職場づくりを行っていくことが大切です。
働き方改革の推進
就業面でのウェルビーイングの向上には、「働き方を労働者が主体的に選択できる」という内容が含まれています。これは、働き方改革の推進にもつながる要素です。従業員のライフスタイルに合わせた働き方を選べる体制を整えたり、多様な働き方を認めたりすることで、働き方改革の推進とウェルビーイングの向上が期待できます。
企業がウェルビーイングに取り組むメリット
企業がウェルビーイングに取り組むことで、多くのメリットを得られます。ここでは、ウェルビーイングに取り組む5つのメリットをご紹介します。
①健康経営の推進
ウェルビーイングは、健康経営の一歩先を行く概念として知られています。健康経営が生活習慣病やメンタルヘルス不全の予防を主な目的とするのに対して、ウェルビーイングは従業員の仕事へのやる気や、組織へのエンゲージメントなどまでを含めて目的とするものだからです。企業がウェルビーイングに取り組めば、健康経営も推進されることになるでしょう。
②企業価値の向上
ウェルビーイングへの積極的な取り組みを公開することで企業価値が向上すれば、売上や人材確保、資金確保といった、多くの面でのメリットを得られます。
ただし、企業価値の向上のためだけにウェルビーイングを利用しようとすると、実態との乖離が起こってかえって問題になる可能性もあります。イメージの向上は、真摯にウェルビーイングに取り組んだ結果として得られるメリットだと考えましょう。
③人的資本経営の実現
「人的資本経営」とは、人材を企業の「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことによって、企業価値の向上を目指す経営方針です。
ウェルビーイングによって従業員の意欲やスキル、定着率を向上させることが、企業価値の向上につながります。
また、人材への投資や人材戦略は、近年、投資家のあいだでも注目を集めています。人的資本経営に力を入れることで、結果的に投資家からの投資が受けやすくなる可能性もあるでしょう。
▼関連記事
>人的資本経営とは?取り組みのポイントとお役立ちツールを紹介!
離職率の低下
ウェルビーイングで働きやすい職場づくりが実現すれば、離職率の低下にもつながります。
仕事を辞めたくなる原因には、「人間関係の問題」「激務でプライベートとの両立ができない」「やりがいが感じられない」といった理由が挙げられます。ウェルビーイングの向上を目指すということは、こうした問題が起こりづらい職場環境を実現するということです。その結果、自然と定着率も上がっていきます。
生産性向上
従業員がやりがいを感じ、前向きに働ける環境を整えることは、スキルアップや生産性の向上につながります。
ある従業員が1時間働いた際に得られる成果は、常に同じではありません。やる気にあふれた日とそうでない日では、仕事の効率や成果に大きな違いが生まれます。
また、ポジティブな感情を持って働くことは、従業員エンゲージメントの向上にもつながります。従業員エンゲージメントとは、従業員が会社に対して貢献したいと思う気持ちや、愛社精神などを指します。ネガティブな気持ちで働くのではなく、積極的に仕事に取り組んでいきたいと思える職場を目指しましょう。
ウェルビーイングの取り入れ方
従業員のウェルビーイングを向上させるためには、具体的に何をすればいいのでしょうか。続いては、ウェルビーイングを取り入れる際の5つの施策をご紹介します。
①セルフチェック・セルフケアを促進させる
ウェルビーイングを取り入れる際には、従業員によるセルフケア・セルフチェックを促進することが大切です。
たとえば有給休暇の取得を促したり、福利厚生でジムを利用できるようにしたりといった取り組みも、セルフケアやセルフチェックを促進するための活動の一環です。そのほか、企業ではセルフチェックの実践方法を従業員に研修する事例も見られています。
②コミュニケーションが取りやすい職場環境を整える
職場はあくまでも仕事をする場ですが、だからといって人間関係をおろそかにしていいわけではありません。
同じ職場で働く従業員同士のコミュニケーションを促進し、良好な人間関係を築けるようにすることは、仲間意識の醸成だけでなくモチベーションの向上や定着率のアップにもつながります。
③福利厚生を充実させる
研修制度の充実や資格取得補助、ワークライフバランスの実現につながる制度の拡充など、福利厚生を充実させることもウェルビーイングにつながります。
④経営目標やビジョンの共有
従業員の仕事へのやる気や、組織へのエンゲージメントまでも含めて目的とするウェルビーイングにおいて、経営目標やビジョンの共有はとても重要です。経営目標やビジョンに従業員が共感し、目的意識ややりがいを持って仕事に取り組めれば、ウェルビーイングを高めることになるからです。
⑤労働環境を整える
安心して働ける職場環境の構築や多様な働き方への対応は、ウェルビーイングを実現するための大切なポイントです。具体的には、フレックスタイム制の導入や働きやすいシフトの実現、労働環境の改善、法令遵守などが挙げられます。従業員が何に不安や不満を抱いているのかを踏まえ、状況に合わせた改善策を検討しましょう。
ウェルビーイングに取り組む際の注意点
ここまではウェルビーイングのメリットや取り入れ方を説明してきましたが、実際に取り組む際には以下の注意点もあります。
- 取り組みを数値化する
- 従業員の声を反映させる
- 従業員自身が心身の健康状態を把握・改善できるようにする
- 継続的な取り組みが必要
- 身体的、精神的、社会的な側面をバランスよく考慮する
取り組みを数値化する
ウェルビーイングに取り組む際は、抽象的なイメージを掲げるのではなく、状態を客観的に把握できるように数値化することが重要です。
たとえば、従業員のストレスレベルを数値化することで、原因や対策を考えやすくなるでしょう。また健康診断の結果を確認すれば、今まで以上に健康に配慮することも可能となります。
人材の確保を目的としている場合は、従業員の労働時間を把握することで、労働環境を改善でき、離職率を下げることにつながります。
従業員の声を反映させる
ウェルビーイングの取り組みにおいては、従業員の声を反映させることも大切です。
たとえば、従業員から健康やストレスレベルについてのヒアリングを行い、その内容を取り入れることによって、より効果的な施策が打ち出せます。
従業員が抱える問題やニーズを把握するには、従業員アンケートを実施するのもひとつの方法です。
従業員自身が心身の健康状態を把握・改善できるようにする
従業員自身が自分で健康状態を把握し、改善できるようにサポートすることも、ウェルビーイングにおいては大切です。
たとえば、健康管理アプリを導入すると、従業員が日常的に自分の健康状態を意識でき、状況に合わせて適切なアドバイスを受けることも可能になります。
継続的な取り組みが必要
ウェルビーイングの効果はすぐに表れるものではないため、継続して取り組むことが重要です。従業員の健康管理を続けることで、ストレスや疲れを軽減し、生産性を向上させることが期待できます。
アンケート調査などを定期的に行い、改善策の検討・実行や効果検証を繰り返していきましょう。
身体的、精神的、社会的な側面をバランスよく考慮する
ウェルビーイングは、身体的・精神的・社会的のすべてが満たされていることが大切です。そのため、どれかひとつに注力するのではなく、これらをバランスよく改善したり良好な状態を維持したりする必要があります。
ここまでに紹介したようなコミュニケーションの円滑化や福利厚生、労働環境の改善など、どれも重要な取り組みといえます。
ウェルビーイングに対する国内外の取り組み6選

ウェルビーイングに対する国内・海外の取り組みの6選をご紹介します。
国内の取り組み
以下、国内での代表的な取り組みです。
味の素
味の素株式会社では、「人財に関するグループポリシー」において、「社員のこころとからだの健康を維持・増進できる職場環境づくり」に努めると明記しています。
「味の素グループで働いていると、自然に健康になる!」というテーマを掲げて、健康経営に取り組んでいます。
具体的な取組内容は以下のとおりです。
- 健康に関する情報ポータル「My Health」
- 従業員が自分の健康データを管理するための専用ポータルを整備
- 健康管理アプリ「カロママプラス」
- AI健康栄養士が健康管理をサポートするスマートフォン用アプリを導入
- 禁煙や受動喫煙対策
- 禁煙セミナーやオンライン禁煙指導プログラムの実施
- 生活習慣予防
- 全事業所で従業員に対して健康的な昼食の提供
ローソン
株式会社ローソンでは、健康宣言において「健康は、本人だけでなく家族を含めた望みであり、会社の発展にとっても欠かせない要素」とし、社長がCHO(チーフ・ヘルス・オフィサー)として健康経営を推進しています。
社長直轄組織の「ローソングループ健康推進センター」を設置、専門知識を持ったスタッフが常駐し、以下の取り組みを行なっています。
- 健康診断の結果にKPIを導入
- 血圧や肝機能などの6項目について、目標値が設定されています。
- 健康増進期間「元気チャレンジ」
- 年に2回実施され、1日あたりの歩数や食事の糖質制限などを実施
- ローソンヘルスケアポイント
- 決まったタスクの実行やe-ラーニングの受講によりポイントが付与されます
- 健康白書の作成
- 全社員の健康状況の集計・分析や、健康増進施策の結果を記載
- 労働安全衛生
- 各店舗で整理・整とん・清掃・清潔・しつけの5Sを推進
デンソー
株式会社デンソーでは、従業員の健康増進を経営課題の一つに据え、健康経営を推進しています。「デンソーグループ健康経営基本方針」を策定し、各職場に「健康リーダー」を配置しています。
具体的な取り組みは以下の通りです。
- 復職支援制度
- 長期にわたり休業した社員の復職に当たり、産業医や上司が連携してサポート
- 生活習慣スコア
- 社員に対して健康診断のデータをもとに「生活習慣スコア」をフィードバック
- 非喫煙者率の向上
- 建物内は全面禁煙、禁煙セミナーや禁煙外来の導入などの喫煙者支援も実施
- 健康増進月間
- 身体測定や歩数競争を行うことで、健康への関心を高める期間
海外の取り組み
海外でのウェルビーイングへの取り組みには以下のような事例があります。
グーグル
グーグルは2018年に「デジタルウェルビーイング」を提唱しました。デジタルウェルビーイングとは、デジタル機器への依存症を防ぐ仕組みを意味します。
グーグルの調べによると、70%以上の人たちが、「テクノロジーと実生活のバランスを改善したい」と考えています。そこで、アンドロイドにデジタルウェルビーイングをサポートする機能を搭載しました。
アンドロイドには以下の機能が搭載されています。
Dashboard
スマホの使用時間やアンロック回数、通知の受信回数を表示し、スマホの使用習慣を見直す
App timer
ユーザーがアプリごとに使用制限時間を設定できる
Do Not Disturbモード
スマホをテーブルに伏せておけば、画面上に表示される不要な情報を非表示に
Wind Downモード
就寝予定時刻になると、Do Not Disturbモードになるのとともに、画面がグレースケールになる
イケア
イケア・ジャパン株式会社では、「ビジネスの中心は人々だ」という考えのもと、3,700人のコワーカーの心身の健康状態やモチベーションのケアを実施。コワーカー自身が自分を大切にし、自分をいたわるセルフケアができるよう、サポートしています。
具体的な取り組みは以下の通りです。
- コワーカーに不安や心配事があるとき、マネージャーなど、コワーカーがいつでも相談できる体制を構築
- コワーカーとの対話や傾聴に関する、マネージャー向けのトレーニングを実施
- ヨガやマインドフルネスのセッション、メンタルヘルスに関するウェビナーやトレーニングの実施
- 有給休暇の取得推進
投資銀行マッコーリー・グループ
投資銀行マッコーリー・グループは、シドニーのオフィス街に本社を移転するにあたり、社員のウェルビーイングとフレキシブルなワークスペースの確保に重きを置きました。具体的には以下の取り組みをしています。
- 屋根をガラスドームとし、建物内全域に自然光を当てる設計に
- 空気はエアコンを利用せず、屋外から新鮮なものを取り込む
- 建物中央にある階段に2階ごとにキッチンアメニティを設置し、社員の運動を喚起する
- ヨガやバレエ、ピラティスなどの運動ができる部屋に、ロッカーやシャワーも設置
- カフェで提供する野菜やフルーツは、現地で生産された安全・良質なものを揃える
ウェルビーイングの向上なら「はたLuck®︎」がおすすめ
店舗のウェルビーイングには、店舗マネジメントツール「はたLuck®」が役立ちます。
はたLuckサービス概要資料、導入事例集

店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。
「はたLuck®︎」の機能の中から、ウェルビーイングにつながる5つの機能をご紹介します。
1. 手軽に感謝の気持ちを伝えられる

「星を贈る」行為を通して、他者への感謝の気持ちを伝えることができます。あらたまってお礼を言うほどではない小さな働きや感謝の気持ちをアプリ上の「星」を送って伝え合うことで、スタッフ同士のコミュニケーションの促進や良好な関係性の構築を実現します。
2. 従業員割の共有・活用促進ができる

従業員割を「クーポン」としてアプリ内で発行できます。頑張ってくれた従業員やアルバイト・パートなどのスタッフに各種優待を提供することで、モチベーションアップにつながります。
3. 経営目標やビジョンを共有できる
「お知らせ」機能では、本部からアルバイト・パートなどのスタッフを含む全従業員に一括して通達を行うことができ、経営目標やビジョンなどの共有も可能です。
4. こまめな情報共有で安心して働ける
「連絡ノート」は、店舗内の情報共有のための機能です。新商品やキャンペーンなどの情報をアプリ上で伝えられ、閲覧したかどうかチェックもできるため、情報共有にかかる手間を大幅に削減できるでしょう。
アプリから手軽に情報を伝えられるので、たまにしか出勤しないシフト制のスタッフへの情報伝達漏れも防げます。スタッフも、必要な情報を把握した状態で安心して業務に入れます。
5. 疑問点があればすぐに確認できる
「マニュアル」機能には、テキスト、画像、動画のマニュアルを格納・閲覧できる機能も搭載しています。
仕事の手順が不安になった際は、いつでも見返すことができますし、新しい仕事に入る前に確認しておくことも可能です。スタッフのスキルアップや働きやすさにつながるという効果もあります。
「はたLuck®︎」でウェルビーイング向上に成功した事例
ここからは、「星を贈る」機能の活用によってウェルビーイングが向上した事例をご紹介します。
スーパーマーケットチェーンを展開する株式会社オオゼキ様では、「はたLuck®︎」によるスタッフ間のコミュニケーション改善に取り組みました。
オオゼキ様は、スタッフのやる気向上による競争力アップを図る中で、「はたLuck®︎」の導入を決めました。通常のチャット機能に加え、「スタッフのモチベーション向上」「連携強化」に役立つ機能を備えていることが決め手になったそうです。
オオゼキ様が「はたLuck®︎」を活用する上で注目したのが、「星を贈る」機能です。まずは、店長が「スタッフ全員に星を送る」という気持ちで積極的にスタッフの良いところを見つけ、「褒める」「感謝する」という習慣を作り出しました。これによって、わずか数ヵ月でスタッフ全体に星を送り合う文化が浸透。店長からスタッフだけでなく、スタッフからの発信も増え、感謝を伝えあう良好な関係の構築や横のつながりの強化に成功しています。
さらに、これまで目立たなかったスタッフや、新人スタッフの小さな気遣いにもスポットライトがあたるようになったことで、スタッフ一人ひとりのやる気の向上や、対面での会話を促す効果が見られるようになったということです。
さらに、「チーム一丸となってがんばろう」という意識は売上にも反映され、年末商戦での目標達成という目に見える成果にもつながっています。
従業員のウェルビーイング向上は企業の重要課題
従業員のウェルビーイング向上は、企業にとって重要な課題です。従業員が感じている不安や不満を拾い上げ、解決するための方法を検討してみてください。
シフトで働くスタッフが多い店舗や支店では、従業員一人ひとりのモチベーションやスキルにまでスポットがあたらないケースもありますが、全体の生産性向上や人材確保のためには、シフトワーカーのウェルビーイング向上にも注力する必要があるでしょう。
「はたLuck®︎」は、シフトワーカーの仕事体験価値の向上につながるサービスを多数提供しています。お気軽にご相談ください。
はたLuckサービス概要資料、導入事例集

店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。

店舗DXコラム編集部
HATALUCKマーケティンググループのスタッフが、記事の企画・執筆・編集を行なっています。店舗や施設を運営する方々向けにシフト作成負担の軽減やコミュニケーション改善、エンゲージメント向上を目的としたDXノウハウや業界の最新情報をお届けします。