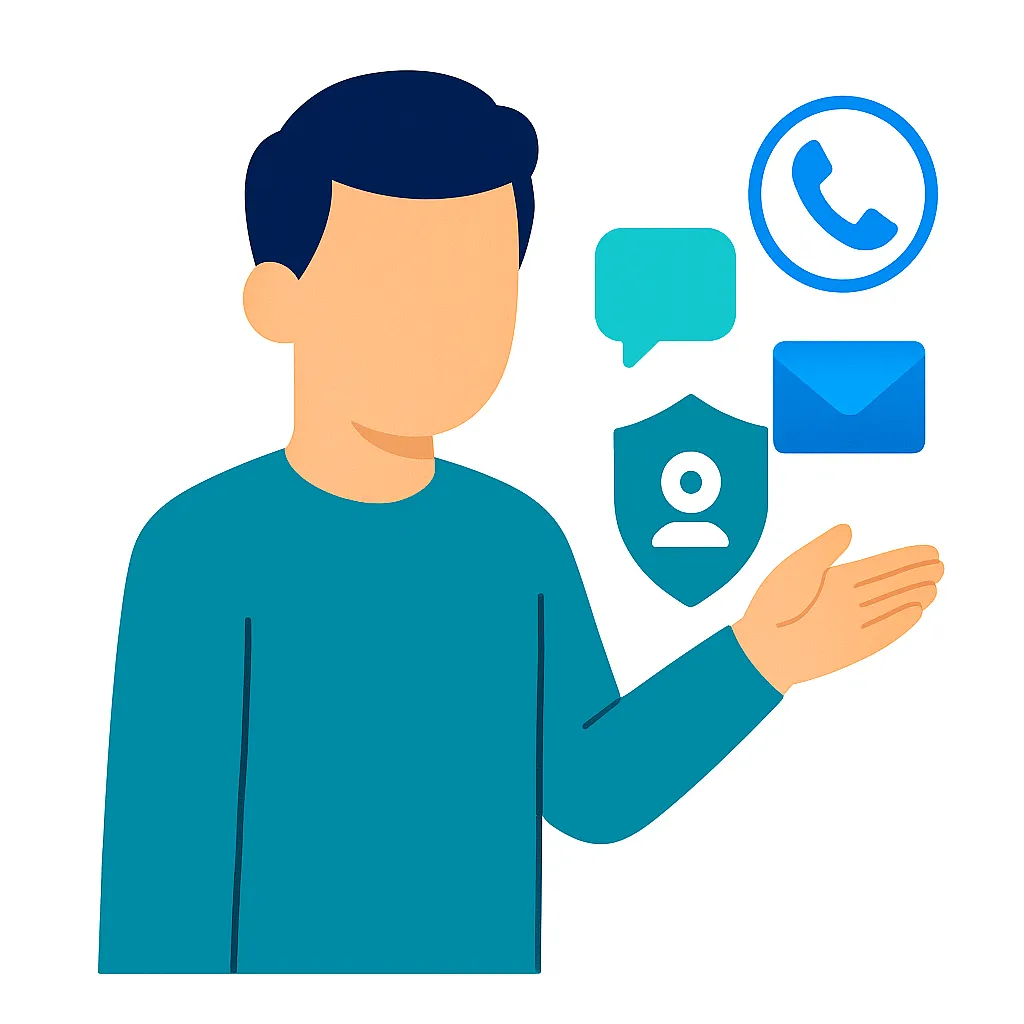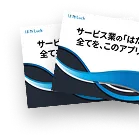店舗運営について悩んでいる店長やSV(スーパーバイザー)も多いのではないでしょうか?
店舗運営とは、小売店や飲食店などの売り場づくりや売上管理、スタッフ管理など店舗の運営・マネジメントを行うこと。しかし、店舗運営においては、スタッフへの業務連絡やシフト作成など課題も少なくありません。
この記事では、店舗運営の仕事内容と抱える課題を解説します。あわせて、業務改善に必要なアプリもご紹介しますので、店舗運営で悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
目次
店舗運営とは
店舗運営とは、小売店や飲食店などの店舗を運営・マネジメントをすることです。店舗運営の仕事内容は、売り場づくりや売上管理、スタッフの管理・教育、在庫・仕入れ管理など多岐にわたります。
複数の店舗をもつ会社の場合には、店舗運営は店長とSV(スーパーバイザー)が二人三脚で行います。SVはエリアマネージャーとも呼ばれ、業態によって5~数十店舗を担当し、本部と店舗の橋渡しの役割を担います。管轄店舗を定期的に巡回し、管轄店舗のバックアップ、 本部からの情報提供、課題発見、管轄エリアの調査などを行いながら、店長の店舗運営をサポートします。
店長の店舗運営における仕事内容

店長は、自分が受け持つ特定の店舗の管理・運営を行います。主な仕事内容は次のとおりです。
売り場づくり
店長の店舗運営における仕事内容としてまず重要なのは売り場づくりです。店内のレイアウトや商品陳列の方法によって、お店のイメージは大きく変わります。売り場づくりがうまくないと、売上の低下につながることもあります。
売り場は整然とキレイに商品をレイアウトすることが重要ですが、ただ整っていればいいというものでもありません。小売店などの場合は購入につなげるためには、お客様に手に取って見てもらうことが必要です。そのため、手に取りたくなるような陳列方法が重要となってきます。
売上管理
売上管理も、店長の重要な仕事のひとつです。売上の集計のほか、何が、いつ、どのくらい売れているのかといった売上の分析や、それにもとづく施策の検討も行います。売上の集計や分析は、人員配置や商品仕入れにもつながる仕事です。
売上管理は、日ごと・週間・月間・年間などの単位で売上を集計し、前期との比較を行うとともに、それぞれであらかじめ設定した目標を達成したかを確認するのが一般的です。売上が落ちている場合には原因を分析し、改善のための施策を立案・実行していきます。
スタッフの管理・教育
スタッフの管理・教育も行わなければなりません。在籍しているスタッフのシフト管理と勤怠管理を行い、スタッフが不足している場合は、求人募集をかけて採用・育成をします。
あわせて、スタッフを定着させるための工夫も欠かせません。スタッフとのコミュニケーションを密にしたり、働きやすい環境を整えたりして、スタッフの定着化を目指します。
多くの飲食店や小売店などでは、パートやアルバイトなどの非正規スタッフを多く雇用しています。パート・アルバイトは出入りが激しい傾向があるため、採用業務は日常的に発生します。スタッフを採用したら、店舗で活躍してもらうための教育が必要です。マニュアル整備や研修・OJTなど、スタッフの教育体制はしっかりと整える必要があります。
📚関連記事を読む
在庫・仕入れ管理
商品の在庫数を管理し、適宜発注を行います。何をどの程度仕入れるのかは、売上予測をもとに決定します。過不足があると売上に影響が出てしまうため、過去のデータにもとづいて慎重に検討しなければいけません。
在庫管理は品質面でも行わなければなりません。売れ残って古くなってしまった商品のセールを実施する、あるいは廃棄するなども在庫管理の一貫です。
SVの店舗運営における仕事内容

SVは、管轄している複数店舗の経営管理を行います。
管轄店舗のバックアップ
SVの店舗運営における仕事内容はまず、管理店舗のバックアップです。売上管理については、店長が単独店舗の売上を管理するのに対し、SVは管轄している複数店舗の売上について管理します。管轄している店舗の生産性をチェックし、より生産性を上げるためにはどうすればいいのかを各店舗の店長といっしょに検討・実行します。
スタッフの管理・教育についてもSVは重要な役割を果たします。店長がスタッフの「指導」をするのに対し、SVは指導というより、スタッフの良き相談相手になって、不満に思っていること、改善したいと思っていることをヒアリングします。ヒアリングの内容に基づいて、スタッフにとってストレスフリーな環境をできる限り整えます。
管轄店舗への情報提供
管轄店舗への情報提供もSVの重要な仕事です。本部の指示や方針は、SVが管轄している店舗の店長に対して伝え、確実に実行できているかを監督します。店舗によってそれぞれ状況が異なるため、各店舗に合わせた内容を適切に伝えることが重要となってきます。
SVが管轄する他店舗の事例やノウハウ・クレーム・ナレッジなどの共有も行います。売上が好調な店舗があれば、その要因を分析し、管轄する他店舗に横展開もしていきます。
管轄店舗の巡回・課題発見
管轄している店舗が問題を抱えている場合、それを吸い上げて課題解決のためのアドバイスや本部との調整を行います。本部と管轄している店舗の橋渡し役として、両者の方針のすり合わせなどを行うのもSVの役割です。
管轄店舗で目覚ましい成果や特筆すべき取り組みがあれば、それらの本部へのフィードバックも行います。他のエリアでも共有し店舗運営の参考にすることで、グループ全体の底上げを図ります。管轄エリア内ではどうしても解決できない課題があれば、本部に相談したうえで、本部の助力を得て解決に取り組みます。
管轄エリアの調査
管轄エリアの調査もSVの重要な役割です。エリア内の競合店へは定期的に出かけ、商品構成や店内レイアウト、セールやイベント、顧客の層などをチェックします。それに応じて、管轄店舗が対抗するための施策を立案・実行します。
また、競合店に限らず、エリア内のリサーチを行います。どのようなお店があるのか、通行人はどのような人たちなのか、交通手段は車なのか、自転車・徒歩なのかなどをリサーチし、管轄店舗の店長と共有しながら改善策のヒントにします。
店舗運営をするうえで抱える課題

店舗運営をするうえで、どのような課題を抱えやすいかを見ていきましょう。
【店長・SV共通の課題】業務連絡が滞る
店舗運営をするうえで抱える課題としてまずあげられるのは、業務連絡が滞ることです。ミーティングなどをしても、シフトが合わない人がいたり、毎日は出勤しないパート・アルバイトがいたりすると全員が揃わないため、連絡が行き届きません。連絡ノートを作成して控室に置くなどしても、なかなかちゃんと見てもらえないうえ、誰が見たかの確認が困難です。
【店長・SV共通の課題】スタッフのエンゲージメントが上がらない
店舗運営を進める中で、スタッフのモチベーションを高く保ち、組織への帰属意識を高めることは欠かせません。しかし、シフト制の勤務体系では、スタッフ同士の交流機会が限られやすく、店舗や会社への愛着が生まれにくい環境になりがちです。
また、業務連絡が行き届かないと、店舗の目標や方針が十分に共有されず、スタッフの仕事への意欲が高まりにくい状況も生じやすいでしょう。結果として、スタッフの定着率の低下や、サービス品質の維持が難しくなるといった問題につながってしまいます。
【店長の課題】シフト作成・管理に労力がかかる
店舗運営をするうえで店長が抱える課題として、シフト作成・管理に労力がかかることがあげられます。具体的には以下のようなことがあるでしょう。
提出期限までにシフト希望を集めるのが大変
シフト作成にあたっては、スタッフからシフト希望を集めるのが大変です。決められた期限までに提出しないスタッフがいたりすると、一人ひとり個別に連絡を取らなければなりません。
手作業でのシフト作成の業務負担
手作業でシフト作成をする場合には、まずスタッフが提出したシフト希望をExcelなどの表へ転記しなくてはなりません。細かな日時を一つひとつ転記するのは大きな手間と時間を要します。そのうえ、転記においてはどうしてもミスが発生しがちです。転記ミスが生じると、スタッフとのトラブルになったり、シフトの再作成が必要になったりしかねません。
能力に合わせたスタッフ配置が難しい
シフト作成にあたっては、曜日別や時間別、あるいは能力別で適正な人数のスタッフを配置しなければなりません。また、人件費が適正なのかも確認が必要です。よくよく考えなければならないため業務の合間にこなすのは難しく、残業したり、家に持ち帰ったりになりがちです。
シフトが法令違反していないかをチェックするのが大変
シフトは労働基準法を満たさなければなりません。たとえば、18歳未満のスタッフは原則として22時以降は働けない、あるいは8時間を超える勤務には1時間の休憩が必要など、労働基準法によるさまざまな制約があります。シフトが労働基準法に違反していないかを、スタッフの一人ひとりについてチェックするのは大変です。
スタッフへシフト連絡するのが難しい
スタッフへ確定シフトを連絡するのは簡単ではありません。シフト表を控室に貼り出すなどの方法だと、頻繁に出勤しないスタッフなどは、シフト表を見るためだけに店舗へ来なければならなくなる場合があります。また、誰がシフト表を見たかの確認も困難です。
急にスタッフが必要になったときに補充が難しい
シフトに入っていたスタッフが急に都合が悪くなる、あるいは体調が悪化するなどして欠員が出た場合の補充も簡単ではありません。スタッフの一人ひとりに電話や私用SNSで連絡して調整することになりますが、都合の良いスタッフがすぐに見つかるとは限りません。
【SVの課題】指示が店舗運営に反映されていない
店舗運営をするうえでのSVの課題として、指示が店舗運営に反映されないことがあげられます。
店舗に指示が伝わったかどうかわからない
本部の指示は、SVが店長に伝えるのが一般的です。しかし、店長がその先、実際に店舗で指示を伝えたのかは、客観的に確認するのが困難です。
指示を店舗に伝達できても、スタッフまで共有するのが難しい
店長がスタッフに本部の指示を伝えるにも、シフトが合わないパート・アルバイトがいたりする場合、全員への指示・徹底は困難です。これはSVにとっても大きな課題です。
店舗運営の課題を解決するには
これまで見てきた店舗運営における課題は、適切な対策を講じることで改善可能です。ここでは、課題に対する具体的な解決策について紹介します。
スタッフへの連絡手法の見直し・ツールの導入
業務連絡の滞りやスタッフのエンゲージメント低下を防ぐには、まず連絡手法の見直しから始める必要があります。
従来の連絡ノートや掲示板だけでなく、スマートフォンアプリやウェブサービスを活用することで、リアルタイムな情報共有が行えるでしょう。既読確認機能を活用したり、重要度のタグ付けをしたりすることで、確実な情報伝達を実現できます。
また、双方向のコミュニケーションを促進することで、スタッフの意見や提案も積極的に取り入れやすくなり、職場の活性化にもつながります。
シフト作成・管理ツールの導入
シフト作成や管理における労力の削減には、専用のツール導入が有効です。シフト管理ツールを利用することで、スタッフのシフト希望収集から確定シフトの通知まで一元管理が可能になります。
また、労働基準法に基づいたチェック機能や人件費の自動計算機能により、法令遵守と経営効率の両立も実現できるでしょう。急な欠勤やシフト変更にも柔軟に対応できるため、代替要員の確保もスムーズに行えるようになります。
指示内容の伝達方法を見直す
本部からの指示が店舗運営に確実に反映されるためには、従来の伝達方法を見直し、より効果的な仕組みを構築しなければなりません。
まず、指示内容をデジタル化し、いつでも確認できる環境を整備したうえで、重要な指示については既読管理を行い、理解度のチェックを実施しましょう。写真や動画も活用することで、より具体的な指示伝達ができるだけでなく、誤解や認識のズレも防ぐことができます。定期的なフォローアップの機会も設けて、確実に指示内容を遂行できているかどうかもチェックするとよいでしょう。
「はたLuck」で店舗運営の課題を解決する
はたLuck は、情報共有やシフト管理など、店舗内の課題を解決できるツールです。ここでは はたLuck がどのように課題を解決するのかをご紹介します。
「トーク機能」でスタッフとのコミュニケーションを深める
はたLuck には、従業員間のコミュニケーションを活性化する「トーク機能」があります。同じ部署やチーム内など、特定のメンバーのみでトークルームを作ることも可能です。全社に共有する必要がない簡単なやり取りなども気軽に行えます。
コミュニケーションが活発になることで、感情面でもプラスに働くほか、仕事も円滑に進めやすくなるでしょう。トーク画面は私用SNSと似たような操作感となっており、誰でも使いやすい点もポイントです。
シフトの回収から連絡まで行える「シフト作成機能」を活用
はたLuck のシフト作成機能を使えば、シフトの回収から作成・確定までをスムーズに行えます。
シフト希望はスタッフが自分のスマートフォンから入力するため、回収の手間がかかりません。期限までに未提出のスタッフにはアラートが届くため、個別連絡の必要もなくなります。
回収されたシフト希望は、シフト作成ツールに自動的に反映されるため、転記は不要、転記ミスもなくなります。また「適正シフト機能」を使えば、店舗別・曜日別・ポジション別などで適正な人数のスタッフを手軽に配置できます。人件費の算出機能や、労働基準法に違反するシフトを組むとアラートを出す機能も搭載されているので、安心してシフトを作成できるのがポイントです。
確定したシフトはアプリ上で確認できるため、シフト確認のためだけにスタッフが店舗へ来る必要はありません。また、確定シフトを誰が見たかも一覧で確認できます。
「欠員募集機能」を使えば、自店舗だけでなく、近隣店舗のスタッフへも募集がかけられるため、よりスピーディーな欠員補充が可能です。
スタッフへの情報共有は「連絡ノート」機能で行う
はたLuck は情報共有や日常のコミュニケーションに役立ちます。「連絡ノート」機能で店長がどのように業務連絡を伝え、スタッフの誰がその連絡を確認したかは、SVがアプリもしくは管理画面上で確認できます。そのため、これまでSVから把握しづらかった店舗での情報共有状況が、はっきりと可視化されます。
「トーク機能」は一般のチャットツールと同様のやり取りができる機能です。スタンプや絵文字なども送りながらコミュニケーションが取れるため、日常の運営やイベントなどのさまざまな話題について、スタッフ同士で話し合えます。もちろん、SVもそのやり取りに参加することもできます。
エンゲージメントサーベイ機能を活用できる
はたLuck にはチェーン店をはじめとした多店舗企業の本部と店舗、従業員をつなぐ機能のひとつとして、「はたLuck エンゲージメントプログラム for Workplace」が搭載されています。
従業員に対して2週間に1度のペースで簡単なアンケートを行い、はたLuck アプリの利用データを組み合わせて分析。導き出された課題に対し改善アクションを行うことで職場のマネジメント力を向上させ、従業員のモチベーションアップや離職率の低下を目指します。
簡易なエンゲージメントサーベイであっても、従業員が回答することに負担を感じてしまうと、どうしても回答率が下がります。しかし、はたLuck はシフト作成をはじめとしたコミュニケーションツールとして日常的に使用されるため、シフトをやりとりするときと同様の感覚で従業員が回答を行うことができ、高い回収率が期待できます。
はたLuck の利用状況に応じたアドバイスができる
はたLuck の「レポート」機能を使えば、アプリの利用状況から店長やスタッフの行動データを分析できます。
たとえば、はたLuck 上のコミュニケーションから、スタッフ同士の距離感や関係性を示すネットワーク図を表示できます。ネットワーク図を見て、もしコミュニティから外れているスタッフがいれば、店長などからのフォローやアドバイスをするなどの対応も可能です。
ツールを活用して店舗運営を効率化しよう
店長とSVが二人三脚で、売り場づくりや売上管理、スタッフ管理などをしていく店舗運営。業務連絡が滞る、あるいはシフト作成・管理に時間がかかるといった課題を抱えがちです。
はたLuck なら、これらの課題を解決できます。はたLuck の活用で、店舗運営を効率化していきましょう。
はたLuckサービス概要資料、導入事例集

店舗サービス業向け、商業施設向け、それぞれのサービス概要資料をご用意しています。導入事例集も一緒にダウンロードが可能です。

店舗DXコラム編集部
HATALUCKマーケティンググループのスタッフが、記事の企画・執筆・編集を行なっています。店舗や施設を運営する方々向けにシフト作成負担の軽減やコミュニケーション改善、エンゲージメント向上を目的としたDXノウハウや業界の最新情報をお届けします。